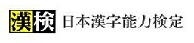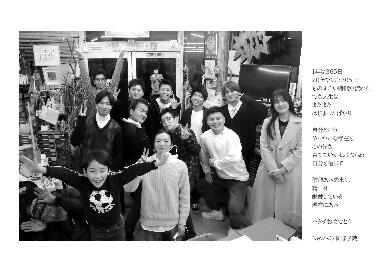明日に向かって、今・・・


★塾長コーヒーブレイク ★2018年3月以前★
私たちは明日に向かって
生かされる存在である
詩やおはなしを書くのを意識したのは、
確か、小5のときだったように思います。
読書と作文の指導が国語の授業の中心で、
その時の先生からはずいぶんと褒められ
励まされたのを覚えています。
本はただ単に読むだけではなく、
深く読み込んで、心の中に呑み込んで、
牛が反芻するようにそのおはなしの内容を
考える習慣が出来上がったのもこの頃かも知れません。
するとどうでしょう。
中学数学で初めて習う証明問題は得意になれたのです。
算数の成績は芳しくなかったのですが、
中学以降の数学は得意分野になりました。
合同や相似などの証明を苦手となる生徒は少なくありません。
そのような生徒は小学生の時からの
読書・作文の学習が不足していたように思えます。
読む力と書く力・・・これが新しい学力観となってくるので、
NEW KGでも国語力の強化に力を入れていきたいと思います。
50年経った今でも、書く事は苦になりません。
詩も創作しています。昨夜も新しい詩が書けました。
ご笑読くだされば幸いです。
2018/3/10 篠島 実
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
私(わたくし)たちは明日に向かって生かされる存在である
私たちは今日まで生きて来たのではない
私たちは今日まで生きてみたのでもない
私たちは今日まで森羅万象に生かされて来たのだ。
君は君だけの努力で幸福感を得たのではない
君は君の知らない多勢の人々に支えられて
生きて来られたのだから、
したがって、君の幸せは
その人々に感謝しながら
彼らと共有しなければならないのだ。
目に見えない自分とのつながりを
これからは意識し、
見つける努力を怠ってはいけないのだ。
あなたは今とても悲しい気持ちになっているのだろう
こんなにも努力してきたのに
目的を達成できなかった。
でもしかし、
あなただけのせいではない
したがって、そんなに自分を責めないでよいのだ
あなたはやれるだけのことを精一杯、
最後までやり遂げたのだから
今日は涙が涸れ果てるまで泣いて悔しがっていいんだ
そうしたら、ゆっくり床に入って眠ろう。
私たちはけっして過去には戻れないことは
誰だって知っている。
しかし
過去を少しずつ取り戻しながら
明日に向かって一歩ずつ進んでいくしかないのだ。
今は、
心の中のエネルギーを蓄えるために
たっぷりと心を休ませる必要がある。
まだまだこれからなんだ、あなたは
あなたの人生は始まったばかりなのだから
苦しく悲しいときにうろたえることなく
涙で心を満たし隅ずみまで洗うことだ
大きな声で泣くことはけっして、
恥ずかしいことではないのだ。
私たちもあなたと共に涙している
あなたは一人ぼっちではないのだ。
外では夜の雨がぱらぱらと降ってきた
昨夜は冷たい雨が天から
激しく叩きつけるように降っていた。
まるで明日のあなたの悲しみを予知して
同情するかのように降っていた。
早春の寒い夜に
厚い雲が垂れ込め
銀河の光は遮られているけれど
この黒雲の上には
万物の根源である宇宙が広がっている。
見えるものだけを見ても何も解決しない
見えないものを想像する努力が
今の私たちには
いたく重要な現代なのだ。
現代社会は病んでいる・・・
君たち、あなたたちも少しは気がついているだろうか。
目先の楽しみや、幸福を求め
自分さえ金持ちになればよい、
自分さえ幸せになれば良いと
その場限りの刹那的に日々を送り
政治に無関心となり
選挙にも行かない人が多勢になってしまった。
自分の幸福だけを追求する人は
未来の人々から
けっして生かされていただけない、と思っている
私たちはもちろん
自分の楽しみや満足や幸福を求めるのが当然だけれど
これから生まれてくる未来びとに喜ばれるような行動を
するか、しないかによって
私たちの明日の人生が決定されていくこの真理を
60年生かされてきたわたしは
みなさんに一番訴えて、学習させたい。
最後にもう一度・・・
私たちは生きているのではない、
生かされているのです。
そして
明日に向かって、生かされ続けられるように
見えない大きな力の存在を意識して、
今を生きていかなければならないのです。
わたしはこの真理を
宮沢賢治という人物を研究していくなかで
だいぶ前に見つけたのです。
2018年3月9日埼玉県公立高校合格発表の夜に
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
PS★新しい学年に向かって、今・・・
NEW KGの春期講習で
よりよい学習のやり方をGetしよう♪*゜
早寝、早起き・・・三文の得・・・
成績をスピードアップさせるコツかも
知れません♪*
学習塾の仕事を初めて僕はかれこれ39年になります。
夜の仕事なものですっかり夜型人間になってしまいました。
中学生のころ(1972年ごろ)は、
ヘラブナ釣りを趣味にしていたせいか、
近所の沼に学校が始まる前の午前5時ごろから
2時間程釣りを楽しんでいたものです。
中学時代は超朝型人間だったのです。
幾人かの爺(じい)さんたちも早朝の釣りを楽しんでいて、
いろいろ釣りの極意を教えてもらったりもしました。
爺さんといえども同じ趣味を楽しむ仲間でありますので、
たくさんの釣り仲間ができました。
古き良き時代の思い出です。
■ ■ ■
現在の僕はまた朝型人間に戻れました。
昨年2月、研修学院の移転のために内装工事が朝から始まるので、
朝早く起きなければならなくなり、
それと同時に、大宮の幼稚園に勤務する娘を早朝に車で送ることになり、
1週間程朝6時前には起床せざるを得なくなりました。
階段から転けて歩くのが大変になったからです。
そして、3代目となる犬(ファルーク・ボーダーコリー)を
飼うことになり、
毎朝、1時間はファルークと一緒に散歩するのが
すっかり習慣になったのも朝型人間に戻れるきっかけとなったようです。
お犬さまは昔から大好きなので、
お犬さまと一緒に朝の瑞々しい太陽の光を浴びて
散歩するのはとてもよい1日の始まりとなります。
そんなこんなで、朝型人間に変身でき、
自分の身体はより健康になれ、心の良い変化も起こりました。
■ ■ ■
授業が終わって生徒が帰ったあとに
夜中の2時過ぎまで仕事をしていましたが、
それを午前中に済ませています。
昼食をいただいた後は20分程度昼寝をし、
すると、また新しい1日が始まる気分になれ、
授業の終わる午後10時までは脳みそがシャットダウンしないで済みます。
以前は教室で徹夜することも少なくなかったのですが、
午前中に仕事をした方が能率がよいのです。
急ぎの仕事がないときは紅茶を飲みながら読書をしています。
夜、お酒を呑みながら読書するよりもだらだらせずに早く読めます。
新しい教室に移転してから朝型人間に戻れたことは僕にとって、とても喜ばしいことです。
■ ■ ■
先日、インターネットで次のような記事が目にとまり、なるほどと思いました。
「朝型と夜型の健康格差なぜ?」
「夜型の子はなぜ成績が悪くなるのか?」
2017年1月14日 毎日新聞
柴田重信 / 早稲田大学教授・田原優 / カリフォルニア大学ロサンゼルス校助教
引用>>>
……全体的な結論として、夜型の子供は、
小・中学生、高校生、大学生のどの年代でも成績が悪い、
という結果が出ました。
その差は大学よりも小学生〜高校生においてより顕著でした。
大学生は小中高生に比べ、自立しており、
時間割も自分で決めることができ、さらに授業への出席も厳しくないので、
夜型の学生も適応しやすいからではないかと考えられます。
それに対し、小中高生は授業開始も早く、
夜型の子供がより社会的時差ボケを経験しやすく、
それに伴う睡眠不足や睡眠の質の低下、
午前中の授業の不適応などが、
成績低下につながっているのではないかと推測できます。
>引用終
■ ■ ■
テストの前日に提出のワークが終わらず
夜遅くまで勉強する・・・夜中まで、布団の中でゲームやスマホをする、
などはNGなんです。
1日24時間は誰にも平等に与えられています。
その24時間をどのように使うのか・・・
どのような毎日を過ごすのか、は大きな課題です。
自分の欲望をコントロールして、
よい習慣を身に付ける努力は
怠ってはいけないと強く思います。(2018/2/20篠島 実)
PS・公立高校受験生・・・
あと1週間程度で本番の入試です。
受験勉強は終わりがなく、切りがないので、
焦る気持ちもわかりますが、
早寝早起きを実行していきましょう♪*゚
決して2011.3.11を忘れない!
気仙沼市立大島小学校と保育園おひさまにご縁があり、
6年前より復興のための支援を微力ながら行っています。
研修学院の売上の一部を遣わせていただいています。
12月はクリスマスのプレゼントとして太陽のエネルギーを
たっぷり蓄えたみかんを子どもたちの人数分贈っています。
2011.311の東日本大震災の津波による被害は想像を絶し、
6年たった現在でも完全には復興できていません。
若い人たちが立ち去り、過疎化が深刻です。
そういう現実の中で、
地元で頑張っている人々を応援することは
とても重要だと思います。
気仙沼は火災がひどかったのですが、
原発事故を起こした場所に比べればまだましだ、、、と話す人もいます。
原発が事故を起こせば放射能の汚染によって、
二度と戻れない場所になり、故郷を追われて、
いまだに、生活が安定されない方も数多くいます。
困ったらお互い様・・・
少しでも震災で困っている人々に
これからも支援を続けていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。(2017/12/20 篠島 実)
・・・家康と妙見菩薩、武甲山と夜祭、そして、僕・・・
埼玉県の西には広大な秩父の森と山地があります。
この豊かな森林資源に注目し、江戸に城を構えたのが徳川家康でした。
その時代は石油よりも木材が重要なエネルギー資源であり
都市を維持する上ではなくてはならないものだったのです。
秩父で切り出した木材を筏(いかだ)にし、
荒川へ流し8時間程度で江戸まで到着します。
自然エネルギーにも家康は注目していたのです。
▲▲▲家康と妙見菩薩と秩父夜祭と武甲山▲▲▲
武田信玄に秩父は一度占拠され、
地元民の心の拠り所、秩父神社は燃やされてしまったのですが、
家康は真っ先に秩父神社を再建させています。
秩父神社の御神体山(神奈備山・かんなびやま)が武甲山。
この山はハワイの方の海底火山でしたが、
太平洋プレートの移動にともない2億年前に
秩父で起き上がるように隆起し誕生した珊瑚礁の化石、
石灰岩の山です。
巨大な亀の甲羅(北の守護神…玄武)を思わせる台形の独立峰は、
家康が信仰していた不動の星、
北辰の女神、妙見菩薩が降り立つ山に見えたのでしょう
(妙見菩薩の乗り物が玄武・・・亀なのです)。
江戸時代では秩父神社を妙見宮、武甲山を妙見山と名づけています。
12月3日の秩父夜祭は秩父神社の例大祭の付け祭り。
動く陽明門と言われるほど、
6基の山車(だし…秩父では屋台・笠鉾と呼ぶ。
約300年前に現在の形になった)の飾りつけは
息を呑むほど美しいのです。
妙見様は養蚕の女神でもあります。
田んぼの少ない秩父のその当時の主要産業、
養蚕(絹糸を作るために相当な重労働が強いられていた)の
繁盛を願う人々の思いが盛大な夜祭にさせたと想像します。
日本一の絹市が12月1日から数日間続き、
遠くの商人の多くが買い付けに来て、夜祭を盛り上げたことでしょう。
▲▲▲秩父夜祭の目的▲▲▲
昨年、この夜祭は世界遺産に登録されました。
秩父夜祭の重要な目的が、五穀豊穣、養蚕繁盛をもたらせてくれた水の神、
男神の龍神に感謝を込めて武甲山の大蛇窪へ還すことです
(蛇は冬眠しますから。春になって今宮神社の龍神祭で里にお迎えする祭があり、
龍神が運んできた水を秩父神社は分けてもらい、
お田植えの神事を行う祭りも300年以上続いている)。
実は、この秩父夜祭は武甲山の男神を還す前に、
年に一度、妙見菩薩と逢引(デート)をさせるお祭りでもあるのです。
このことを話せば長くなるので今日はやめておきますが、
たかが夜祭でも、いろいろなことが隠させており、
その一つ一つを掘り起こしていくと、
日本の歴史や世界の歴史の詳細、
特に民俗学的な庶民の信仰や行動がみえてきたりするので
歴史好きの者にとってはとてもたのしいことです。
▲▲チチブイワザクラは宇宙でたったここだけに咲く▲▲
武甲山は秩父で誕生して2億歳。
アウストラロピテクスが700万年前。
琵琶湖は550万年前。
富士山(士・ツワモノ・ども富・アマ・た具して登らせ不死の薬を燃やした山
・・・竹取物語より・・・)が10万年前に形成されました。
そう考えると武甲山の履歴はものすごく、
この山だけで進化した植物や昆虫が少なくありません。
日本のガラパゴスと言ってもいいほどで、他の山よりも植物の多様性は豊富で、
僕は、毎月登りに行っていますが、そのときどきの山野草に癒されています。
チチブイワザクラは宇宙でたったここだけに咲くプリムラの新種です。
ユリは日本が原産らしいのですが、
その原種がスカシユリ。
武甲山のミヤマスカシユリもここで進化したことでしょう。
ウスイロヤマブキソウやブコウマメサクラなど名前を上げれば、
この紙面一杯になってしまうほどです。
▲▲▲僕と武甲山と山頂破壊反対運動▲▲▲
武甲山の山頂を破壊することを初めて知ったのが
1979年1月17日の新聞記事でした。
セメントの原料である石灰岩を大量に採掘するためには
山頂を崩さなければならないことが理由です。
生物学的、民俗学的にも重要な武甲山の山頂は百年後、
千年後の人々に残してあげなければならないと、
その記事を読んだ僕は直感します。
自分の大学受験の日をキャンセルして、
山頂破壊反対運動のためのドキュメンタリー映画を作るために
武甲山へテント担いで山友達を誘って3泊4日、8mmムービーで撮影し、
編集し、20分の「1979年武甲山を見据える」のドキュメンタリー映画を
4月に県庁所在地で上映し、山頂破壊反対運動の狼煙(のろし)としました。
たくさん集めて秩父に乗り込む計画があったのですが、
5人しか集まらず挫折、翌年9月には山頂を破壊されてしまいました。
世の中と自分自身に絶望するも、それ以後、年に1度以上は武甲山に登り、
武甲山が痛めつけられている履歴を写真で記録してきました。
38年間の僕が撮影した武甲山の写真はマスコミにも注目されつつあります。
1979年以降、年に1回以上武甲山上映ライブを催し、南は九州の福岡県、
北は宮城県気仙沼と、声がかかれば時間を融通し喜んで駆けつけています。
▲▲▲これからが武甲山の正念場▲▲▲
武甲山の悲劇は、現代文明の終焉を予感させます。
何百年も大切にしてきたものを壊すのはよくない・・・
特に自然破壊はほどほどにしなければ僕たちや
子孫たちの未来が危なくなるとつくづく思うのです。
実は武甲山の問題はこれからが正念場だと考えています。
地質学者的タモリも感動した武甲山と秩父に興味関心を持たれる人々が
増えることを切望します。
どうぞ武甲山をこれからもよろしくお願い致します。(2017/11/22 篠島 実)
・・・因果応報・・・興味深い四字熟語
四字熟語を苦手とする生徒が少なくありません。意味が複雑で難解なものが多いからでしょうか。
でもしかし、人類3000年の文化や処世術がぎっしりと凝縮されたものが多く、
この熟語が何百年も大切にされてきた意味とわけを深く学べば、
正しく生きていく法則や定理がはっきりと見えてくるのでは、と思います。
ふと、四字熟語についてwebで検索してみました。
すると、「四字熟語一覧の検索ランキング」が目にとまりました。
https://dictionary.goo.ne.jp/より 10/21 am7:30現在
1位 阿鼻叫喚
2位 因果応報
3位 慇懃無礼
4位 百花繚乱
5位 前途多難
6位 不撓不屈
7位 疑心暗鬼
8位 乾坤一擲
9位 唯一無二
10位 森羅万象
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
さあ、みなさんはこの検索ベスト10の中でご存知の四字熟語があるでしょうか。
わからないのがあったら是非調べてみてくださいね。
ぼくは検索1位の「阿鼻叫喚」の意味があやふやだったので調べてみました。
その結果、すごい意味だったことを思い出せました。
>>>意味<<<
(あびきょうかん)非常な辛苦の中で号泣し、救いを求めるさま。非常に悲惨でむごたらしいさま。
地獄に落ちた亡者が、責め苦に堪えられずに大声で泣きわめくような状況の意から。
▽「阿鼻」は仏教で説く八熱地獄の無間(むけん)地獄。
現世で父母を殺すなど最悪の大罪を犯した者が落ちて、猛火に身を焼かれる地獄。
「叫喚」は泣き叫ぶこと。一説に八熱地獄の一つの大叫喚地獄(釜(かま)ゆでの地獄)の意。
《阿鼻叫喚の用例》幾十万にも及ぶ広島在住の無辜むこの民を
一瞬にして阿鼻叫喚の地獄に晒(さら)したということであります。
<井伏鱒二・黒い雨・・・広島原爆の悲劇をものがたった小説>
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
このベスト10の中でぼくが日常の思索の中でよく登場する熟語が2つ含まれています。
その一つは「森羅万象」。
(しんらばんしょう)天地間に存在する、数限りないすべてのもの(万物)や事象。
▽「森羅」は樹木が限りなく茂り並ぶ意で、たくさん連なること。
「万象」はすべての形あるもの、有形のものの意。森羅万象の出典『法句経(ほっくきょう)』
ぼくたちは大自然の恩恵を受けなければ決して生きていくことができず、
生物の多様性の中で自分は生かされていることを確認する重要な言葉だと思っています。
次に「因果応報」。
(いんがおうほう)人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。
▽もと仏教語。行為の善悪に応じて、その報いがあること。現在では悪いほうに用いられることが多い。
「因」は因縁の意で、原因のこと。「果」は果報の意で、原因によって生じた結果や報いのこと。
《因果応報の出典》『大慈恩寺三蔵法師伝(だいじおんじさんぞうほうしでん)』
因果応報を使われた有名な小説に永井荷風・榎物語があるそうです。
『月日を経るに従い、これぞまさしく因果応報の戒めなるべくやと、
自然に観念いたすように相成り申し候。』この小説の核心をつく一文なのでしょう。
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
四字熟語は仏教のお経を元に作られたものが少なくありません。
人が人として生きていく上で大切にしなければならないことをぎゅぎゅっと詰め込んでいると思います。
この「因果応報」の教えはとても重要です。
人の見ていないところで悪いことをする人は少なくありません。
しかし、天・・・宇宙・・・神仏はいつもぼくたちを見守っています。
他者がいない空間と時間でよい行いをするか、悪い行いをするのか・・・
それの影響が後の人生の中で現れる、というものすごい教えです。
人が見ているところでよい行いをするのは、他者から褒められたい、
よい報酬を得たい…という刹那的な自己中心的な幼稚な思考が原因です。
人の見ていないところでよい行いをする人は、誰かに評価されたり、ご褒美をもらいたいからそれを行うのではなく、
いつも見守ってくださる天(神仏)に感謝する行動の現れなのでしょう。
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
誰もいない孤独な時間に、しっかりと勉強する生徒はぐんぐん成績が伸びていきます。
逆に、人の目を盗んで、スマホばかり操作し、クソみたいなゲームばかりを行う生徒は、
テストで良い結果が出ず、そして低学力になっていきます。
これこそが「因果応報」であります。
ぜひみなさんもこの教えの意味とわけをしっかりと学習して、
そして、充実したすてきな人生が歩めますことをお祈りいたします。
2017/10/21 冷たい雨ばかりの朝に…篠島 実
NEW KGの看板完成♪*゜
NEW KGの看板がやっとできました。
ぼくの友人でもある看板デザイナーの木村さん(浦和高校出身・写真左)が
彼の友人と共に作製してくださいました。
三百年前の秩父の古民家の廃材を今年譲り受け、
それをどうにか活用できないだろうかと相談していました。
ぼくは我がままな人間だと認めていますが、
その我がままに付き合っていただける友人や
知人が少なくないことは嬉しいことです。
その廃材の土台に、ステンレスの切り文字でKGのロゴを作りました。
金属加工では川口で3本指に入られる
杉田さん(写真左から2番目)が担当されました。
金属加工のアーティストとして数々の展覧会も行っています。
そして、NEWKGの内装をしてくださった
イスラエル人のダニーさん(左から3番目)も
秩父から手伝いに駆けつけて下さいました。
古くからの友人の多くが、NEWKGを盛り上げて下さっていますので、
今後、彼らの期待にも応えられるようにがんばらないと…
と気が引き締まる思いです。
2017/8/22 研修学院塾長 篠島 実
仮想ではない、
現実の世界で自分を活躍させよう♪*゜
仮想現実・・・virtual reality(バーチャルリアリティー)と英語でいいます。
インターネットの普及とスマホの普及でこの「仮想現実」の世界で生きる人々が増えました。
ぼくはそれをとても危惧しています。
現実の世界で生きていかなければ、
ぼくたちはみんなアバター的になってしまうのです。
自分を変身させる上ではアバターは便利な分身となりますが
子ども達にとっては危険な分身だと思います。
ぼくは「禁止」するのが嫌いなので
原則として自由にさせて子ども達を観察しています。
授業中のスマホの操作は当然ながら禁止させていますが、
本当はスマホなんて小学生中学生には持たせたくないです。
現実がわからなくなるからです。
現実感覚が鈍くなっている大人たちも
増えているように思える出来事や事件が最近目立ってきました。
ぼくは塾長の仕事の他にカメラマンの仕事と
ミュージッシャンの仕事も掛け持ちしていますが、
どれもリアリティーな仕事です。
特に、ギターを弾いたり唄を歌ったりのLIVEは
リアリティーなことです。
ぼくは幼い時から今まで、
仮想現実的な世界ではなく
常に現実に根ざした世界で活動してこられたことに
幸いを感じています。
還暦を迎える歳になっても
現実の中でたのしく生きられているからです。
ところで・・・
今の中高生はスマホの悪影響で、
現実を直視できない人が多勢です。
気温のちょっとした変化で
体調を崩したりする生徒が最近増えていますが、
自分の身体とのやり取りがだめなんだと思うのです。
健康の管理はまずは自分自身で考えなければなりません。
日頃の食事を含め、自分の体の中の大自然に対して謙虚になり、
それの保護を意識しないとすぐに体調を崩すのだとぼくは考えています。
自分の健康はそれこそ現実の世界のことです。
現実を見つめること・・・これは重要なことなので、
何かにつけ子供たちに説教をしています。
しかし、スマホの悪い文化の勢いにはぼくはお手上げです。
小中学生に対してはスマホ禁止令を出したいぐらいです。
ぼくがもし文部科学大臣になったら、一番の仕事はそれです。
子ども達の未来を輝かせるためです。
ぼくが大臣になれる可能性は0.00001%なので、
どうにか仮想現実にどっぷりなこどもたちを救うために
あの手この手を考えていますが、なかなかいい手が見つかりません。
しかし、「ハンドスピナー」と「パワーボール」の重力を利用した
単純な遊具は効果を発揮しています。
ぼくが40年近く集めてきた民族楽器も効果的です。
現実の世界の中で音を楽しむのに簡単な楽器は功を奏します。
小さい太鼓のボンゴや、アフリカンの素朴な楽器・・・。
そんなに大きな音が出ないので、
他の人の勉強の邪魔にはならなく、
そのような楽器を紹介して現実の空間で体験させています。
ぼくは小6のときにギターに魅せられ
独学でその楽器の演奏を極めてきました。
指が痛くなってもがんばりました。上手になりたいとの一心で・・・。
現実の世界で修行をすれば指も身体もいたくなるのです。
それがまさにリアリティーなことなのです。
現実の世界で生きていると、
その疲れはとても心地よい疲れとなります。
楽器演奏の他、スポーツをがんばることも現実に生きることにつながります。
スマホは程々に・・・これからも声を挙げ、
ぼくはがんばっていきますので
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします♪*゜(2017/6/21夏至)
PS・期末テストで自己ベスト更新を!!Fight♪*゜
ともにがんばりたい春です♪*゜
30年続けてきた本町の教室から
川口旧寿町に移転して1ヶ月が経過しました。
ようやくぼくの気持ちも落ち着いてきたようです。
あたふたした期間で、幾人かの生徒と保護者のみなさんに、
いたらないことが多々有り申しわけなく思っています。
お詫び申し上げます。
引越しと旧KGの引渡しの作業は思っていたとおり大変でしたが、
現塾生・職員はもちろんのこと、
卒塾生や、OBの先生、ぼくの友人も
手伝いに来てくださりどうにかこうにか、
目的を達成できました。
ぼく一人の力、また職員数人の力では
成し遂げられなかったことだとつくづく感じています。
お手伝いいただけた方に改めて御礼申し上げます。
■ ■ ■
新しくなったKGの生徒心得を
3月8日の新学期ガイダンスで確認しましたが、
この心得は先生たちの心得でもあります。
「人は一人では生きていけない・・・
誰もがよりよく人と関わりお互いの個性を理解し、
受け入れ、リスペクトし、強みを分かち合い、
弱みを補い合い、生きていることを
こころから喜べる毎日を過ごす権利を私たちは持っています」から
始まりますが、そこに書かれてあることの意味とわけを意識して、
さらに深く考察していくことにぼくたちの
生きていく目的が隠されていると思います。
自分さえ楽しめて、
そして幸せになればよいと考え行動するのは
ニンゲンだったら当然なのでしょうが
(そのような大人たちが増殖しているみたいです・・・)、
その考えの延長線上には「戦争」が
待っているのだと思えてなりません。
■ ■ ■
奪い合えば争いが絶えないからです。
奪い合うことから分け合うこと、
富を独り占めするのではなく、
それを多くの人々に分け合うことをみんなが実行したら、
きっと、もっとすてきな世界が広がっていくのでしょう。
ぼくはそれを信じてこれからも生きていきたいと思っています。
知識や智慧もそうです。
勉強をみんなに教えていて、
早く理解しマスターする生徒もいますが、
なかなか意味とわけを理解できず困ってしまう生徒もいます。
同じに教えているのに不思議なのですが、
みんなが同じように同じ時間でできるようになる・・・というのは
幻想に過ぎないと悟っています(あたりまえですね)。
■ ■ ■
早く理解してできるようになった人はちょっと立ち止まって、
まだできてない人に教えてあげてください、とぼくは頼んだりします。
人に教えるのは、ものすごくたいへんなことだとわかると思います。
しかし、教えることによって、
もっと深く理解が進むこともたびたびありますので、
互いに実力が高まっていく効果があります。
「自分は何を勉強しても理解が遅いし、成績もよくない・・・」と
心の中で悲しみ、勉強を諦めかけている生徒もいるかも知れません。
でもしかし、自分ひとりで悩まずに友人や知人、
学校やKGの先生に尋ねてみましょう。
自力で全てのことをできないことは、
その昔、お坊さんの親鸞(しんらん)が悟ったことです。
今日食べた食事の材料を全て自分でつくることは不可能で、
日々の命をつなぐ食事は多くの見えないところで
働いている人々のおかげなのです。
他者の見えない力をいただいてぼくたちは今日を過ごせるし、
明日も生きていけるのでした。
■ ■ ■
どうか「自分さえよければよい・・・」という
刹那的な行動をコントロールして、
多くの友人たちと共に幸せになることに価値をみいだし
行動を起こしてください。
そして、今僕が語っていることを多くの人々に広めてください。
今いる友人ともっと親しくなれるでしょうし、
すてきで充実したお互いの人生が約束されることでしょう。
::::::::::::::PS::::::::::::::
GWが終われば、すぐそこは中間テスト!!
はやめに提出しなければならない課題のワークをこなしていこう♪*゜
先を見通して生きていくことは、自立する第一歩。
何のために勉強するのか・・・その一つの答えは巣立つためです。
いつかは、みんなも親元を離れて自分で生きていかなければなりません。
いつまでも親のすねをかじって生きていくことはできないのです。
そのためにも頭脳を鍛えなければなりません。
一人立ちして立派な人生を幸せな人生を歩んで欲しい…との思いで
KGの授業料を払ってくださっている親御さんの気持ちを
もう少し考えてください。
m ( _ _ )m 研修学院 塾長 篠島 実
答えは、、、風の中にあった♪*゜
かれこれ10年前の出来事である。
前の同居人だったコーギーのマーキュリー(故犬)と
強風の中お散歩をしていたとき、
ある紙切れが僕の顔に飛んできた。
何なんだ!と思って、
その紙切れに書かれてある言の葉を読み出す。
学習塾の経営にとても行き詰っていたときであり、
これらの言の葉は、僕の心をとらえ、
何度も反復して読んでしまった。
いったいぜんたい自分って何なんだ、、、
自分の存在している意味とわけは何だったのか・・・
しどろもどろに自問自答する自分がそこにいた。
その後、学習塾はそのときの危機を乗り越えられたのは幸いだった。
そして、1979年に作ったドキュメンタリー映画「武甲山」の
再編集を行った。
そして、秩父に乗り込んで武甲山の写真展を
展開する中で多くの心ある人々と出遭う。
2011.3.11・・・原発事故・・・
いてもたってもいられない気持ちになる。
第七艦隊の去った後に、ご縁のある離島の気仙沼大島へ
支援物資を届けにいく・・・
放射能の怖さについて、みんなに嫌がられながらも、
啓蒙することを積極的に行動してきた。
昨年、再び、学習塾の経営危機、、、
高額の家賃を半分以下にできるところを偶然にも発見する。
そして、ぼくの考えている移転の条件の95%も満たしていた
(必ず起こる関東大震災への対策など・・・)。
面積は50坪から34坪で半分にはならない。
16坪ほど減ってしまうだけだ。
そして、こんなにすてきな秩父の森の中にいるような教室が、
多くの方々の見えない力と協力と応援で格安に完成した。
今の生徒たちと職員のほぼ全員は新しい教室の完成を
祝福してくれていることは嬉しい限りだ。
不思議な見えない力の中にぼくは主体性をなくし、
ただひたすらに秩父・武甲山保護のために行動を起こし、
それに没頭していった約40年間。
不思議なとても不思議な物語が展開され、
そのシナリオのなかにぼくは主人公になったり、
脇役になったり、いろいろな仮面をかぶせられたり、
精神分裂的な「はちゃめちゃな自分のペルソナ」の
一つ一つを見つめ直す時間もないぐらいだ。
自然現象に同化してしまい、人々の困惑の中に同化してしまい、
世の中の憂いと喜びの中に自分が同化されてしまう。
それこそ、「どうか」しちゃっている。
今日(こんにち)の自分は、今日のKG(けんしゅう学院)は
10年前の風に運ばれた
この一枚の紙切れにあったことを思い出した。
答えは風の中にあったのだ。
▼▲▼▲▼▲紙切れに書かれてあった言葉たち▲▼▲▼▲
人のためを考え、人に喜んでいただけることを考えていると
心はどんどん明るくなっていきます。
逆に自分のことや自分の喜びばかりを考えていると、
心は不安に包まれて、どんどん暗くなります。
商売でも、お客様に喜んでいただこうと努力していると、
繁盛して自分が喜べるようになります。
しかし、自分が儲かることばかり考えていると、
お客様はだんだん来なくなり、
自分の心も暗くなって、ついには行き詰まります。
一般に、相手にとって都合のよいことは、
自分にとっては都合が悪いことが多いものです。
しかし、相手に喜んでいただこうと努力している人には、
相手の喜びは自分の喜びですから、共に喜べることになります。
明るい心も暗い心も、それを相手に与えると、
やがて山彦の如く自分に帰ってきます。
したがって、共に喜べる明るい心は、
物事の順調な展開を約束し、
どちらかが一方しか喜べない暗い心は、
その逆の結果を生みます。・・・・
移転のお知らせ
この場所、本町3丁目で30年近く過ごしてきましたが、
5年前の大震災でのダメージもあり、
特に、隣のビルの耐震構造に疑問を持っています。
大震災で外壁はひび割れし、応急処置を施してあるも、
近い将来、首都圏を襲うであろう
直下型地震の際には倒壊する危険が大であると思っています。
大切なお子様を預かっている以上、万が一の大震災に備える意味で、
より安全な場所に来年3月に移転することを
決定しましたのでお知らせします。
移転先はホームセンター「ケーヨーD2」の隣りで、
かつて、デイリーヤマザキというコンビニだったところです。
今年の7月までは読売新聞販売所でした。
現在の研修学院と同じく1階で、
34坪の広さを確保できます。ビルではなく、
鉄骨の2階建てで、オーナーさんが2階に住んでいます。
オーナーさんは秩父の宝登山神社とご縁があり、
ぼくもその神社の宮司さんと面識があります。
ぼくのこれまでの人生は
秩父のご縁で事が運ばれることがとても多いようです。
武甲山の自然保護活動を37年間行ってきたご縁かもしれません。
2階は木造建で、倒壊の心配は現在の場所よりも少ないと思います。
また、すぐ近くには大震災のときの一時避難所があり、
荒川の土手に近く万が一のときにも
生徒を安全な場所に避難させることができることも
移転を決断した大きな理由です。
現在の教室から直線距離で500m程度、
川口駅まで徒歩10分以内です。
内装等は秩父の友人たちが協力していただけます。
ハウスシックの原因になる壁紙は使わず、
秩父の杉板を使います。
教室の中で森林浴ができるイメージです。
木の香りのする空間で学習すると効果が大きいという研究者もいます。
とても安価に内装をしていただけることになり、
ぼくの多くの友人・知人が移転にともなって
たくさん協力いただけるのも有り難いことです。
来年の3月2日が公立入試で、3日が面接試験。
3月2日までは現在のところで入試対策授業や面接対策レッスンを行います。
3月3日〜3月7日は引越し。
3月8日より新学年をスタートします。
場所も変わり、内装も一変しますので、
学習指導のシステムもリニューアルさせようと考えております。
現在でも、個別指導塾以上に個人指導を行っていますが、
生徒一人ひとりの学習をバージョンアップさせ、よりよい指導となるように、
さらに個々が満足できるような指導をつくり上げていきたいと思っています。
今後とも、研修学院をよろしくお願い申し上げます。
なお、電話番号は現在と変わりません。
2016年12月21日 研修学院塾長 篠島 実
人間は考える葦である
ぼくは大学で、情報学、コンピュータ、教育学と心理学、
そして哲学を主に学びました。
かれこれ37年前のことです。
文系と理系の大学を両方卒業したようなもので、
かなり得したと思います。
その当時のコンピュータはメモリーが少なく、
外部記憶装置はカセットテープレコーダー。
それでも苦労して、
課題に出されたジャンケンゲームのプログラムを作り、
これは面白いと思うも、
コンピュータってやつは
僕との相性が非常に悪いと思いました。
■ ■ ■
「コンピュータに使われる人間にはならないぞ」との思いで、
その勉強からは早々とおさらばし、
その後、教育学へのめり込みます。
教育学はこの日本がよりよい国家になるための教育を
どのようにするのか・・・みたいな内容の授業が多く、
右翼関係の教授が大学にのさばっており、
僕みたな大江健三郎の書物をよく読んで、
正しいことを発言したりすれば、
「お前は左翼か」と怒られ、
「ぼくは右でも左でもないのです。ぼくは前です」といって、
その教授の授業をボイコット。単位は当然もらえませんでした。
このような教授の授業をまじめにノートしている人が
学校の先生になっていると思えばぞっとするのです。
教育学はうさんくさく、次にぼくは心理学に向かいます。
学習心理学の授業で、ねずみを使った実験をさせられました。
そして「ねずみの実験からわかったことを
子供たちの教育を念頭において考察せよ」という課題が出て、
ぼくは「ねずみと人間のこどもとはそもそも違うものであるから、
この考察をすることは無駄である」とレポートし、教授を困らせました。
しかし、「キミは面白い」と言って下さり、
その後可愛がっていただきました。
しかし、心理学はぼくにはあわないと思って次に哲学に向かい、
本当に学びたかったものに出逢えます。
コンピュータから教育学、心理学、哲学・・・だんだん過去に戻ってしまいました。
■ ■ ■
比較文化論の先生の話が面白く、
「サルトル、キリスト、最澄・・・この3人の「愛」のとらえ方は同じだ」
のような切り口で自分のしどろもどろの研究途上の話を
つばを飛ばしながら広い教室に3人しかいない授業で
熱弁を語っている。
授業というよりは先生の自己満足の場でしたが、
その若い先生から情熱をたくさんもらえ、
ぼくも比較文化論を研究したくなります。
このジャンルはまずは哲学の歴史上の有名な人の書物を
たくさん読まなければなりません。
したがって、たくさん読みました。
ソクラテスやプラトン、アリストテレス、ルソーやデカルト、
パスカル、カントやヘーゲル、マルクス、ベンサム、
JSミルやデューイ、フッサール、メルロポンテ、サルトル、
レヴィ=ストロースやハイデッガーなどなど。
するとどうでしょう・・・今までこだわって学んできた
コンピュータのプログラムもハード的な仕組みも、
教育学も心理学も、
古くからの哲学者の考察した言葉のなかで
それらの理論を包み込んでいることに気づくのです。
人間が人間として生きていく中で、
どんなに科学技術が発達しようとも忘れてはいけないことを
多くの哲人は三千年前よりぼくたちにメッセージを残しています。
「無知の知を知れ」「汝自身を知れ」「自然にかえれ」
「身体と心を分離するなかれ」
「自分は歴史上に実存し歴史をつくる重要な一人であることを自覚せよ。
見て見ぬふりの無関心は人として最低な行為である」
「大切な教えはそれぞれの民族の言葉の中に構造化されている」・・・
過去の哲学者の中でもパスカルの言葉はぼくのこころの拠所になっています。
■ ■ ■
「人間は考える葦である」
人はほんとうにか弱い存在です。
でもしかし、、、自分をいとも簡単に押しつぶそうとする
大自然の宇宙を、世界を、
地震や津波をイメージし思考することがぼくたちにはできます。
思考することによって自分を押しつぶそうとするものを
逆に包み込むことができます。
そういうことを考えればか弱い葦の如きものであっても
偉大な力をぼくたちは持っていることになるのだと解釈し、
思考し続けることが
自分自身を生き続けることになると思っています。
理系でも文系でもそのもとのもとは
哲学だと認識し、過去の哲人の書物を読めば
新しく新鮮で色あせていないものに出逢えることでしょう。
2016.11.23の朝日新聞朝刊に
ぼくの大好きなパスカルの話題が出ていましたのでご紹介します。
(2016/11/23 篠島 実)
■ ■ ■
連載:折々のことば 2016年11月23日 朝日新聞
人間の弱さは、
それを知っている人たちよりは、
それを知らない人たちにおいて、
ずっとよく現(あら)われている (パスカル)
おのれの弱さに向きあうのは難しい。つい虚勢をはったり、
ものごとを傲慢(ごうまん)に言い切ったりする。
自分をそのままで保てないのだ。
自分の弱さを知る人は、
自分が誰かに支えられていることもよく知る。
だから他人の弱さにもすぐ気づき、
すっと手を差し伸べられる。
17世紀フランスの思想家の「パンセ」
(前田陽一・由木康訳)から。(鷲田清一)
■ ■ ■
PS・実力をつけること、、、
とにかく、基礎学力をしっかり身に着けよう。
そして思考力(哲学力・・・ものの見かた考えかた力)も、ね
・・・そのためのけんしゅう冬期講習♪*゚ m(_ _)m
Blowin’ In The Wind 2016/10/20
今年のノーベル文学賞は
アメリカのシンガー・ソングライター、ボブ・ディランに決まり、
僕は嬉しく思いました。
彼は、百年以上にわたる同賞の歴史の中でシンガー・ソングライターとして
初めて受賞することになったからです。
スウェーデン・アカデミーの事務局長は2016年10月13日、発表に際し、
ディランがつむぎ出す詩の数々は、
古代ギリシャの詩人ホメロスらの創作活動と共通していると高く評価されました。
古くから詩人は、自身の作品が単に読まれるだけでなく
「(朗読などによって)聞かれること、実演されることを念頭に創作を行ってきた。
ディランも同じだ」と語っています。
しかし、ディランはこの受賞を拒否。
反骨精神をここでも見せつけました。
フランスの実存主義哲学者のサルトルもノーベル文学賞を拒否しています(1964年)。
サルトルは後日次のように語っています。
「ノーベル文学賞を拒否した理由…
わたしは自分が死ぬ前に人が"サルトル"を神聖化することを望まないからです。
いかなる芸術家も、いかなる作家も、そしていかなる人も、
生きている間に神聖化されるだけの価値のある人はいません。
なぜならば、人は全てを変えてしまうだけの自由と力をいつも持っているからです」
ボブ・ディランも同じ理由かもしれません。
ギター片手にハーモニカをホルダーに付け、
自分の創った詩を歌う彼のスタイルに影響を受け、
僕も一人三役で若い時からLIVEを行っています。
自分の感じたことを歌にしてみることの大切さを彼から教わったのです。
彼の歌の中で一番のお気に入りは「風に吹かれて」です。
とても意味の深い詩であります。
1962年の音楽雑誌にこの詩を書いた動機を述べています。
「世の中で一番の悪党は、間違っているものを見て、
それが間違っていると頭でわかっていても、目を背けるやつだ。
俺はまだ21歳だが、そういう大人が大勢いすぎることがわかったんだ」
僕に多大なる影響を与えたこの歌の和訳を試みてみました。
英文のオリジナルと比較して、
もっと良い訳があったら是非指摘してください。
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
Blowin' In The Wind(風に吹かれて) 作詞/ Bob Dylan(ボブ・ディラン)
How many roads must a man walk down 人はどれ程の道を歩めば
Before you call him a man? 一人の人間として認められるのか
How many seas must a white dove sail 平和の白い鳩はどれ程海を渡れば
Before she sleeps in the sand? 安心して砂浜で眠ることができるのか
How many times must the cannon bolls fly どれだけの砲弾が飛び交えば
Betore they're forever banned? 戦争は永久に禁止されるのか
The answer, my friend, is blowin' in the wind 友よ、答えは風に吹かれて
The answer is blowin' in the wind 答えはその風の中にある
How many years can a mountain exist 山が海に流されなくなってしまうのに、
Before it's washed to the sea? どのくらいの時間がかかるのか
How many years some people exist 為政者たちは、いつになったら
Before they're allowed to be free? 人々に自由を与えるのか
How many times a man turn his head 見ないふりをしながら
Pretending he just doesn't see? 人はどれくらい顔を背けるのか
The answer, my friend, is blowin' in the wind 友よ、答えは風に吹かれて
The answer is blowin' in the wind 答えはその風の中にある
How many times must a man look up 人はどれくらい見上げれば
before he can see the sky? 空が見えるのか
How many ears must one man have 一人一人にいくつの耳をつければ、
Before he can hear people cry? 人々の悲しみを聞くことができるのか
How many deaths will it take till he knows 戦争でどれだけの死人を見れば、
That too many people have died? これは死に過ぎだと気づくのか
The answer, my friend, is blowin' in the wind 友よ、答えは風に吹かれて
The answer is blowin' in the wind 答えはその風の中にある
インディアン・フルート 2016/9/20
2年前からぼくの耳は調子悪く、
ギターの音を正確に聞き取れなくなってしまいました。
しかし、たまたま秩父の友人宅で
聞いた尺八の音楽は違和感なく耳に入ってきたのです。
そして、その後、
インディアンフルートの音楽に生まれて初めて出逢い、
尺八と同様に、耳に心地よく入ってきます。
どうしてもこのフルートを手に入れたくて、WEBで検索し、
2か月前に手に入れ毎日30分はこの笛を吹いています。
未だにどれがドでレでミかわからないのですが、
インディアンが録音したものを聞いて
耳コピでそれを真似して吹いています。
耳の調子はだいぶ良くなってきました。
実は2年前、難聴もさることながらあまりにも耳鳴りが酷く、
とうとうぼくの大っ嫌いな病院に行きました。
診察結果は「突発性難聴」。
2週間以内なら治しようがあるが、
あなたの場合は1ヶ月以上たっているので直せません、と言われて、
その医者は僕の耳に手を当てることなく、
聴力検査の結果の紙を見てぼくにそのように告げました。
ぼくは悲しくなりました。ぼくの難聴が不治であること以上に、
この医者の態度に悲しくなったのです。
この人はどのような志を持って医者になったのか考えました。
自分が診察して、その結果をどのように伝えるか、その伝え方によって、
患者がどのような精神的なショックを持つか考えられない医者がこの医者であります。
この人の医者としての資格はほとんどないと思った瞬間、
この人はかわいそうな人なんだなと思って、
その医者に手を合わせて、看護師にも手を合わせてぼくは薬の処方箋も貰わずに、
無言で初診料だけ払いその場を去ったことを鮮明に覚えています。
こうなったら、自分の自然治癒力を最大限に発揮して治すしかありません。
食べ物に気を付け、戸田の七福の温泉にほぼ毎日通い温泉療法。
温泉療法ははやく功を奏しました。
そして、このインディアンの笛。
CDを友人から借りて毎日聞き、効果はありましたが、
自分で吹く音色は効果てきめん。
耳鳴りは収まり出し、難聴も改善されつつあります。
この笛のおかげで、自分の耳が復活してくれそうです。
これをきっかけにインディアン(アメリカ先住民族)のことをいろいろと調べ、
子供の教育についてとても示唆的な、
現代人にとって忘れていた大切なことが記されていることに気づきました。
それは次の言葉です。英文も添えておきます。
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
★批判ばかり受けて育った子は非難ばかりします
If a child lives with criticism,He learnes to condemn.
★敵意にみちた中で育った子はだれとでも戦います
If a child lives with hostility,He learnes to fight.
★ひやかしを受けて育った子ははにかみ屋になります
If a child lives with ridicule,He learnes to be shy.
★ねたみを受けて育った子はいつも悪いことをしているような気持ちになります。
If a child lives with shame,He learnes to feel guilty.
★心が寛大な人の中で育った子はがまん強くなります
If a child lives with tolerance,He learnes to be patient.
★はげましを受けて育った子は自信を持ちます
If a child lives with encouragement,He learnes confidence.
★ほめられる中で育った子はいつも感謝することを知ります
If a child lives with praise,He learnes to appreciate.
★公明正大な中で育った子は正義心を持ちます
If a child lives with fairness,He learnes justice.
★思いやりのある中で育った子は信仰心を持ちます
If a child lives with security,He learnes to have faith.
★人に認めてもらえる中で育った子は自分を大事にします。
If a child lives with approval,He learnes to like himself.
★仲間の愛の中で育った子は世界に愛をみつけます
If a child lives with acceptance and friendship,He learnes to find love in the world.
この言葉に共鳴し、子育てを見直すきっかけとなる方が多数いると願います。
なお、インディアンは大切なことを決定する際、
7代先の子孫をイメージするといいます。
つまり、百年、二百年先の人々に思いを馳せるのです。
このような視点をもった人々が増えれば、
持続可能な社会の実現は可能だとつくづく思います。
(2016/9/20台風16号の夜に・・・篠島 実)
たのしかったボーリング大会2016.8.17

毎年恒例、夏休みのボーリング大会。
テーマは、集中することの大切さ・・・
集中しないとボールはまっすぐに転がらない。
しかし、集中しようと緊張しすぎれば、あるいは、
何が何でもスペアーをとるぞと、肩に力が入り過ぎれば、
溝に落ちてしまう。
なかなか思ったとおりに転がらない。
成績アップを目的にした学習でも、
同じことがいえるかもしれない。
テストでハイスコアーを出したかったら、まずは、
重要事項の暗記だ。そして問題をひたすら練習。
自分の脳みそと手を使ってみないことには仕方がない。
人のやっているのをいくら見ていても
決して上達しないボーリングと同じように。
夏期講習後半戦・・・自分の実力をアップさせるために
ラストスパートだ。Fight!! (2016/8/21篠島 実)
オヤジの形見
今から20年前のことになる。
74歳で死んだオヤジ(大正11年生まれ)の
遺品を整理していたとき、
いつも持ち歩くバッグのなかから
「憲法」と表紙に2文字、小さく印刷されている
B7サイズの小さな冊子が出てきた。
「1974・埼玉県」と裏表紙に印刷されている。
手垢で汚れた小冊子だが、
オヤジがとても大切にされていたことが感じ取れる。
その始めのページに次のようなことが書かれてあった。
■ ■
憲法は生活の盾
埼玉県知事 畑 和(はた やわら)
「憲法を知らなくても生活できる」
よくこういう人がいます。果たしてそうでしょうか。
ある憲法学者は憲法に次のようにいっています。
「憲法の実用的な意味は、まずそれが、
国民の基本的な権利を保証し、
すべての国民の生活の盾となることにある。
民主憲法は、思想や良心や学問の自由を守り、
言論の自由を尊重して、文化の基礎を支えてくれる。
不合理な差別の扱いを禁じ、法の下の平等を約束している」と。
私はこの説に賛成です。
ですから、冒頭に掲げたような言を吐く人には、
むしろ「憲法を知らなくても生活できるまでに、
私たちの生活は憲法によって守られている」のだといいたいし、
憲法を知らなくてもよいという考えが、
その心の中心にあったとしたら、
一刻も早くそうした考えを捨てていただきたいとお願いしたい。
もしこの憲法が失われたり、棚上げされたとしたら、
私たちの人間らしい生活は同時に失われてしまうといってよいのです。
(中略)機会あるごとにお読みいただくことによって、
この世界にも比類のない民主憲法、
平和憲法をみなさんとともに
守ってまいりたいと思っています。
■ ■
盧溝橋事件(日中戦争勃発)・南京大虐殺が起きた 1937年、
そのときオヤジは15歳だった。
その時代にはこの憲法はなく、
主権を天皇とした大日本帝国憲法だった。
国家総動員法が成立したのは翌年で、
日本は完全に軍国主義化された。
オヤジも徴兵され、お国のために戦った。
友人の多くは戦死したが、オヤジは九死に一生を得、
今僕は奇跡的に存在している。
オヤジは戦争のことをあまり語らなかったが、
お国のために死んだ友人が不憫(ふびん)でならない……と
つぶやいていたのを覚えている。
戦争によって傷つけられた心が
そう簡単にいや癒されるものではなく、
そんなオヤジが死ぬまで
いつも持ち歩いていたのが「日本国憲法」だった。
その平和憲法は、
傷ついた心を大いに癒してくれたのに違いない。
そして、その小冊子は神社のお守り以上に
「お守り」だったのだろう。
大切な形見として僕も常に持ち歩いている。
■ ■
ビートルズがつくった映画、
サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド
(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)
にこういう場面がある。
暴力をボクシングのグローブに見立て、
「グローブからGを取り去ろう。
GLOVE−G=LOVE…愛が残るんだ。」
僕たちは愛の中で生まれ、
見えない愛の力で今日まで生きてこられた。
愛はとても難しい抽象的な観念だが、
「愛は地球を救う」のは嘘ではないと思うし、
戦争、暴力、搾取のない世界の実現は
僕たちの愛の力で成し遂げられると信じている。
他者の幸せを思い、他者に喜ばれることが
自分の幸せになると思う心が
愛の重要な一面だと僕は考えている。
現在の日本国憲法、
9条に戦争放棄を掲げた平和憲法は
世界中の市民の理想でもある。
そして、その憲法の中に
僕たちの人間らしい生活、
人としての生きる権利が保証されている。
この平和憲法が変えられようとしているきな臭い現在、
憲法の意味とわけを深く考え、
僕たちのための憲法であり続けるように
努力しなければならないとつくづく思う。
決して、戦争をやりたがっている人々の
憲法に変えてはならない。
それは、僕の死んだオヤジや、
戦争で無念の死を遂げた多くの人々、
そして、
今は亡き元県知事の畑さん(1996年没)を供養するためにも。
2016/6/22 篠島 実
プラスチック ラブ 2016/5/20
自分の人生を大きく変える出来事は
誰にでもあると思います。
ぼくにも当然ありました。
1979年1月の出来事は今でも鮮明に記憶しています。
大失恋してしばらくたったある日に、
食欲はあまりなかったのですが、
南浦和駅内の立ち食いそば屋で素うどんを食べたときのことです。
このそば屋のうどんは、汁もあっさりして美味しく、
うどんは手打ち風で歯ごたえがとても良かったので、
このお店ができてから駅を利用するたびに寄っていました。
その日にどんぶりを手にした瞬間、
「なんだ、この軽さは!?」と思いました。
せとものどんぶりからプラスチックに変わっていたのです。
中身のうどんも汁も変わっていないのに、
何だかとてもまずく感じてしまいました。
最後、汁をすすって飲んだ時の、
あのプラスチックどんぶりと唇が接触した時の
気味の悪い感触は今でも忘れません。
そば屋のおばちゃんとは顔なじみになっていたので
「このどんぶりだとまずく感じるよ」と話しかけたら、
「やっぱりそうよね・・・・・・。ごめんね、本社が勝手に決めてしまって。
でもね、このプラスチックのどんぶりは軽いし、
割れないし、私らにとってはとても便利なんだよ。」
……そうか、そうなんだ。これからますます世の中は
このようにプラスチック化されてしまうのか、とつくづく思い、
その日の夜に「プラスチックラブ」という唄ができました。
近代文明に懐疑的になった日でもあります。
科学技術の進歩は本当にニンゲンを幸せにするのか、
近代化のために自然を破壊していくことを
許していいのだろうかという問題を
心からはっきりと意識した日でもあります。
毎日の何気ない体験から、その意味とわけを感じ取り、
思索を深めることによって、その後の生き方に変化をもたらすことも
あるのだなと思っています。(2016/5/20篠島 実)
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
プラスチック ラブ 詩/曲 しのじまみのる
形だけを気にして
カッコつける男
着飾ることしか知らずに
街をうろつく女
真似ることしかできない
薄っぺらなニンゲン
時間を節約するから
ニセモノがまかり通る
みんなみんなプラスチック
恋までがプラスチック
人生までもプラスチック
ボロボロになってもプラスチック
ホンモノなんていらないさ
ホンモノなんていらないさ
合理的で経済的で
ああそれから大量生産
つくられた流行りに乗っかって
つくられた流行りに乗っかって
いらなくなったら
その場で捨ててしまえ
みんなみんなプラスチック
恋までがプラスチック
人生までもプラスチック
ボロボロになってもプラスチック
みんなみんなプラスチック
全てがプラスチックに変わってしまう
恋までが形ばかり
プラスチックラブしかできやしない
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
PS・①中間テスト対策、みんながんばっています。
中間終わったら、すぐに期末テストです。
日頃の学習をもう少し充実させましょう♪
「意味とわけ」を意識するのだ!!
巨大地震への備えを・・・
九州地方の熊本と大分で
大きな地震が起き、
甚大な被害になってしまいました。
この災害で大切な命を落とされた方へ
ご冥福をお祈りするとともに、
避難生活をされている約10万人の皆様に
お見舞い申し上げます。
■ ■ ■
今回の地震は、
とてつもなく長い断層帯…中央構造線上で起きました。
九州では阿蘇山の手前で二股に分かれ
一方は熊本を経由して長崎の五島、
そして沖縄につながっています。
もう他方は鹿児島の川内原発付近に伸びています。
M6.4で最大震度7を記録した4月14日21時26分の前震も、
4月16日 1時25分のM7.1で甚大なダメージを受けた本震も
震源の深さは10kmと浅かったのです。
震源が深ければ、余震の回数に比例して地震が弱まり、
収束するのも早いのですが、震源が浅いと、
余震が次の余震を呼び、なかなか大地は静まらないようです。
あるところの断層が破壊されれば、
それに連鎖して、周辺の断層の破壊につながるのです。
これを書いているのは4月20日ですが、
今まで600回以上の有感地震があり、
いつ大地が静まるのかは
気象庁の人も前例がないのでわからないと言っていました。
5年前、東日本大震災の震源は
三陸沖、日本海溝の海底だったのですが、
その深さはやはり10kmと浅く、
したがって、余震の回数がとても多かったのを記憶しています。
(直下型ではなかったので、地震での家屋の倒壊は少なかった。)
地球の内部は非常に高温で、
地表の下にはゲル状(液体と固体の中間)のマントルが対流をおこし、
46億年前の地球誕生後から、陸地は移動を続けてきました。
特に日本列島の下にはいくつかのプレートが常に動いており、
それによって断層にひずみが貯められ、
断層の破壊へとつながり大地震を引き起こします。

構造線といわれているものは巨大地震を引き起こす断層帯です。
先の4月3日のNHKスペシャルでは、
「次は列島のどこで巨大地震が起きるのか」を
テーマに放送しました。
最新の研究から見えてきた新たな構造線を説明し、
九州も危ないことを予想していたのです。(※図2・図3参照)
日本列島は、地震と火山の島国。
大昔よりこの中央構造線上で、
直下型の大地震が起きてきました。
したがって、大地を鎮めるため、
古くからこの構造線上に神社を建てられてきたのでしょう。
川口の近くでは大宮の氷川神社があります。(※図1参照)

この中央構造線を昔の人は龍(大蛇)に例えていたそうで、
龍脈ともいわれています。
鹿島神社の要石(かなめ石)は
龍の頭を押さえている石という言い伝えがあります。
今年1月にアメリカの地質学者が、
この中央構造線の東は、
5年前の3.11の震源域付近まで続いていることを発表されました。
M9というものすごいエネルギーを出した地震ですので、
この中央構造線上の活断層に
そのエネルギーが保存されている可能性もあるのです。
この列島のどこで
次の巨大直下型地震が起きても
不思議ではないということです。
今回の熊本大分大震災を他人事とは思わず、
私たちも地震への備えを十分に行わなければならないと考えます。
研修学院では、まずは命の根源の水と海の塩、米などを備蓄し、
大震災へ備えています。
備えあれば憂いなし・・・ご家庭でももう一度、
地震への備えを見直すことをおすすめします。
そして、国は原発事故が起きないように、
危機感を持って、
十分に備えなければなりません。
(2016/4/20 篠島 実)
「スマホ」依存症にご注意!
「スマホ」はとても便利で、一度手にしたらなかなか手放せない。
情報を引き出したり、情報を発信したり、
その携帯性と機能性はすばらしい。
しかし、「スマホ依存症」が増え続ける今日、
そのスマホの弊害に警鐘を鳴らす医者や心理学者が増えてきた。
特に、小中学生に持たせては、低学力をまねき、
20歳ぐらいから老眼になってしまう可能性もある。
寝るときに布団に入ってのスマホは絶対にさせてはいけない。
まっくらな部屋で小さい画面からの
強烈なブルーライトは網膜にダメージを与え、
睡眠障害をもたらす。
何事も程々にすることが大切だ。
スマホの使用によって
起きる病気や弊害についてインターネットで調べましたので
是非お読みください。
▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼ ▲▼
1.ブルーライトによる弊害
ブルーライトはスマホが普及してから
注目されるようになった。
ブルーライトはとても強い可視光線で、
パソコンやスマホのディスプレイから発せられる。
それをずっと浴びていると、角膜を傷つけたり、
体内時計をくるわせて不眠症になる。
2.歩きスマホによる弊害
歩きながらLINEをしたり、
ゲームに夢中になる子どもたちも増えている。
それによって線路への落下、
交通事故、対面衝突などが発生している。
3.記憶力の低下
記憶力の低下も懸念されている。
デジタル機器の利便性の向上により、
主体的に脳を動かすことが少なくなってきたことが要因。
4.腱鞘炎(けんしょうえん)
スマホはタッチパネルにより、手や指の関節を動かす。
頻繁に使用すればするほど、動かす回数は多くなり、
腱鞘炎になってしまう可能性がある。
スマホ腱鞘炎とも呼ばれ、
最近では深刻化している問題。
5.指の変形
スマホは手に持って操作する。
持ち方にもよるが、
指に負担をかけている持ち方をずっとしていると、
次第に指が変形していく。
それによって、
指を思うように動かせなくなり
痛みが走ることもある。
6.首の骨の変形
携帯電話を見るときは、首を下向きにする人がほとんど。
そして、スマホの普及によって
携帯電話の使用頻度が増えた昨今では、
以前よりも首を下に向けている時間が長くなる。
そうすることで、首の骨が変形してしまう。
首の骨は普通は体の前方向に反った形になっている。
しかし、首を下向きにすることによって、
その反りがなくなり、まっすぐになってしまう。
これをストレートネックといい、
肩こりや全身の疲れの原因になる。
Merry Christmas! & Happy New Year!
毎年、クリスマスイブは
朝霞市白百合園の教会のミサに呼ばれ、
カメラマンを務めている。
今年も多くの子ども達と一緒に祈りを捧げて来る。
この白百合園の園長兼牧師、江川博一さん・・・
89歳を感じさせないパワーを持っている。
戦後まもなく、夜間保育を開始し、
夜、路上をさまよっている幼子を保護してきた。
どの保育所も受け付けない、自閉症の子や、
障害を持った子ども達の保育も引き受けている。
現在でも困っている子どもはもちろんのこと、
社会の隅っこに追いやられて
困っている大人たちへも愛の手を差し伸べている。
慈悲の心を真に持ち得て、
愛を実践してきたマザーテレサは世界的に有名だが、
江川牧師も愛に満ちた実践を68年、
埼玉県の朝霞市で継続している。
日本が世界に誇れる一人だと確信している。
かつて、彼とたくさんおしゃべりしたなかで、
とても印象に残っている言葉で
「子どもの騒ぐ声が聞こえないところは
砂漠以上に砂漠だ」がある。
少子化の日本・・・
ますます心の砂漠化が進むいやな予感がする。
「この世からお金がなくなったら、
愛がたくさん残るのだろう」
命よりも経済が重要だと言わんばかりの政治家たちがなんと多いことか。
百年後の未来人の笑顔のために、
どうして、誠実な政治ができないのだろうか。
どんちゃん騒ぎ的なクリスマスではなく、
自分と社会を見つめ直す
この静かで清冽なクリスマスイブは
毎年、ぼくの1年の締めくくりとなる。
「すべての生きているものにとって、
すてきな世界でありますように・・・Merry Christmas!」
「子どもたちの未来に
希望のともしびを・・・
Merry Christmas!」
多くの祈りは
きっと天まで届いてくれることだろう。
絶望よりは希望を・・・(2015/12/20 篠島 実)
♪゜・*:.。. .。.:*・♪゜・*:.。. .。.:*・♪
Happy Happy Xmas (作詞作曲 しのじま みのる)
あの街 この街 お祭り騒ぎ Happy happy Xmas
みんな集まってワイワイがやがや Happy happy Xmas
久しぶりに逢ったね シャンパンもう一杯
今この時を みんなで 生きているってすばらしいことだね
みんな最高のともだち Happy happy Xmas
あいつは来年結婚するんだって Happy、happy Xmas
幸せな二人に乾杯 幸せよ全世界に飛んで行け
これまでいろんなことあったね 喧嘩したこと
たくさんあったっけ…今また、逢えたことはHappy happy Xmas
みんな最高のともだち Happy happy Xmas
Happy happy Xmas 実は最近悩んでいる
本当にこのままでいいのかってね この世の中、なんだか狂ってる
科学の 進歩で 便利な世の中になったけど
その分、僕らは へんな物質に侵されている
今、生きているすべてのものに Happy happy Xmas
Happy happy Xmas小さな愛を下さい
Happy happy Xmas小さな愛を集めたい
一つひとつは 小さくても集まれば
ものすごい力に… 僕らはこの地球を救える
今、生きているすべてのものにHappy happy Xmas
今、生きているすべてのものにHappy happy Xmas
♪゜・*:.。. .。.:*・♪゜・*:.。. .。.:*・♪
未来の私に向かって、今
私が私として生きていく。
誰もが理想とする人生だ。しかし、
私の人生ってのはなかなか手ごわく、
それを獲得するのが意外と難しい。
自分自信を意識すればするほど、苦しみ悩む。
その苦しみや悩みを乗り越えれば、
本当の自分に出逢えることを信じ、とりあえず、
明日も悩みを背負いこんだまま生きてみるしかないのだろうか。
どうしようもなく思い悩みイライラしたら、
無理してそれを解決せずに、
大樹のある林や森の中に逃げ込んでみよう。
山登りならなお良いかもしれない。
何十年何百年も生き抜いている老木は特に、
私たちに生きる勇気を当たり前のように与えてくれる。
その大樹の中にはたくさんの小鳥が息づいており、
チーチー、ジュクジュク・・・などのさえずりに耳を澄ませば、
自分自身に強く固執している愚かさを
気づかせてくれるかも知れない。
悩みの多くは「あれが欲しい」
「あの人がああなって欲しい」という
自分勝手な欲望なので、
そのような自分の都合の良い欲望、
自分だけの喜びを求めるところにそれらの原因がありそうだ。
自分の欲望を一度リセットさせ
本当の自分を取り戻すために、
大昔からそこに息づいている
老木が大いに役立ってくださる。
「今後、何をどうするのか・・・」を
自問自答しながら
私たちは明日も今日と同様に生きていく。
その目的が多くの人びとにも
喜んでいただけるものならば、
未来の人々からもきっとエネルギーをもらえ、
実現できるのでは、と思う。
今までの歴史上の本当に偉大な人々は
そのようなことを全身で感じ取っていたに違いない。
自分自身を正しく見つめる努力は
世界にも深くまなざしを向けることになり、さらに、
隠されている自分の未来を発見することにもつながっていく。
まずは、自分に願い、
そして未来の人々のしあわせも願い、
独りよがりにならずに、
自分の人生を歩んでいきたいと思う。
最後に、息子が生まれた年(1994年)に
つくった唄をご笑読下さい。(2015.11.20 篠島 実)
未来の私に向かって、今
未来の私はどうなっている、
だれもが悩むこと。
今の私を見つめること、
目をそらさずに見つめることさ。
今の私の中に未来の私がいる、
だから、私は私を思うこと、
私に願うこと。
未来の私はどうなっている、
だれもが不安になること、
私は私の不安から逃げ出すものか。
今の私の中に必ず未来が隠されている。
今の私を見つめることは
未来を見つめること。
未来は、突然訪れはしない、
未来は突然、やって来ない。
だから、今、始めるんだ、
明日に向かって…
さあ、今、始めるんだ、
まだまだ、間に合うから…
さあ、明日に向かって、今…
私は私になる。
1991年1月17日の夜に
詩を創ることを意識したのは、
たしか、小学校6年生、11歳のころだと思う。
1970年、中学に入ってからはカレッジフォークソングがブームで、
ギターを覚え、詩に曲をつけては大学生の真似をしていた。
日頃の何気ない風景の唄や、
社会性のある唄も創ってきた。
そのころ人気のあった吉田拓郎や南こうせつ、
岡林信康、六文銭の歌で
お気に入りのやつはクラスのみんなで唄った。
カラオケのない時代だったので、
ギターは重宝された。
ギター1本あれば、みんなで唄えた。
今から思うとすてきな学生時代だったのだろう。
インターネットや携帯電話が
なかったのも幸いしている。
かつてよりは少なくなったものの、
今でも心に込み上がるものが生じたとき、
唄を創っている。
1991年1月17日、
その日はアメリカがイラクを空爆し湾岸戦争が勃発した。
テレビはその様子を一日中特別番組で放送していた。
全世界に配信されたその空爆の映像は
まるでテレビゲームみたいだったことを覚えている。
その日の夜に
ぼくも立ち会う中、娘が誕生した。
病院から一人星空の下帰りながら、次の唄が産まれた。
1991年1月17日の夜に(米大統領に送った手紙より)
世界ではまた争いの火蓋が切られた。
人と人が血を流し、多くの命がかんたんに
失われようとしている。
おとなたちはまた、おろかな一人の考えに
振り回され殺し合うことを選んでしまった。
そんなさなかに
居心地のよい母の中から
私たちの世界へ自分の力をふりしぼって
生まれてきた女の子がここにいる。
爆弾が飛び交う空の下で
今まさに生まれんとする子どもたちが
きっとたくさんいるだろう。
さあ、やめなさい、
力で人を制することを。
さあ、やめなさい、
過去の過ちを二度と繰り返さないために。
今生まれてくる子どもたちの産声を
全世界から集めて花火をつくろう。
その花火を白い家の前で打ち上げよう。
めざめて欲しい、
思い出して欲しい、
あなたがこの世界に
生まれてきた夜のことを。
めざめて欲しい、
思い出して欲しい、
あなたがこの世界に
生まれてきた夜のことを。
(詞・篠島 実)
PS1
芸術の秋。創作の秋でもあります。
絵を創作したり、詩や唄を作ったり、
物語をつくったりしてみよう♪
与えられている音楽や画像、
ゲームを消費するばかりだけでは人生はつまらないぞ!
自分の創造する力を身につけることは、
人間として生きていく上でいたく大切なことだと思います。
PS2・期末テストで自己ベスト更新を!Fight!♪*゜!
見えない力
ぼくたちは見えない力に支えられている。
たとえば地球の重力。
落ち着いて座っていられるのも
この見えない力だ。
さらに月の引力。
もし、月がいなかったとしたら
地球の自転速度は3倍になり、1日は8時間。
風の強い嵐の毎日で、
1000m以上の山は吹き飛び、
飛ぶ鳥は飛べず、
地を這うものしか
生き残れない地球になってしまう。
この落ち着いた夏の夜は、
実は月の見えない力だったのだ。
夜空いっぱいに輝く
名もない星のどれをとっても
ぼくたちにとって無駄な星はない。
どんなに小さな星であっても
ぼくたちを
見えない力で応援してくれている。
宇宙の質量保存の法則からすれば
ぼくたちも一つの星くず。
ぼくたちも 見えない力を出している。
たとえば、言葉。
言葉を遣ってあいさつを交わすこと。
信頼関係の第一歩は「おはよう」から始まる。
さらに、
自分を支えてくれている人々に対して
心込めて「ありがとう」と
感謝する言葉を投げかけること。
忘れてはいけないのが
目の前の困っている人々を助け支えること。
そして、
謙虚な心を持って他のものと関わること。
それらの個人の行動は
見えない力となり、
多くの人々を
幸せな気持ちにさせることにつながり
それが結果として
自分自身の最高の幸福となることだろう。
ぼくたちは、皆、それぞれ、
幸せのためにこの星に生まれてきた。
幸せを与え、
幸せを味わい、
次の世代にバトンタッチしていく。
そして、ぼくたちは
互の見えない力で支え合っているのだ。
見えない力が複雑にからみあい
秩序をつくって支え合っているのが
実は宇宙であり大自然だ。
ぼくたちも
宇宙の多様性の秩序の中に身を委ねている。
だから 自然にかえらなければならない。
したがって 自然を破壊してはならない。
破壊してしまったら
戻って自らを取り戻すことが
不可能になってしまう。
もう これ以上 自然を痛めつけるのは
程々にしなければならない。
それは、けっしてお金では買うことのできない
ぼくたちの素朴な幸せを確保するためだ。
宇宙から、見えない力で訴えているのが聞こえる。
時には
宇宙から届く音のない声を聞いてみないか。
夏の夜空の
たとえば、ペルセウス座あたりを眺めながら。(2015/7/20篠島 実)
・・・何のために生まれてきたのか・・・
「何のために自分は生まれてきたのか?」
このことばを意識したのは、ぼくが中学3年生のときだった。
アメリカ軍が北ベトナムに空爆を再開した時代(1972年)である。
「どうして人間は愚かな戦争をやめないのだろう」という疑問とともに、
「何のために自分は生まれてきたのか?」を
本気で考え出したことを覚えている。
そして、手当たりしだい本を手にし読書した。
そのころは、ベトナム戦争の激化にともない、
核戦争に発展し、世界が崩壊に向かう危機感を多くの人々が感じていた。
そのような時代だったから、
学校の先生もベトナム戦争のことをたくさん話され、
日本の平和憲法については公民の授業で多くの時間を使って授業した。
世界中に日本国憲法第九条が広まれば、
愚かな戦争はこの人類からなくなる・・・と、
一つ希望の光が見えた。
だからぼくは、九条も含め、日本の平和憲法は
なんとしても守らなければならないとつくづく思っている。
■ ■ ■
戦争に限らず、人間はちょっとしたことでつまらない口論になり、
それがヒートアップすれば喧嘩になってしてしまう。
さっきまで親しかった友人と絶交してしまうこともある。
喧嘩が暴力的になり、それに国家が加担すれば軍事行動を起こし
戦争に発展してしまう恐れもある。
力で、暴力で人を制することはほんとうに愚かなことで、
力で制した後は空しさが残ることだろう。
ベトナム戦争は、1973年1月29日アメリカ軍の全面撤退後、
1975年4月30日に北ベトナム軍がサイゴンを陥落させ終結となった。
核戦争まで発展しなくて、安堵したものだった。
しかし、その後、アメリカ軍が撒いた枯葉剤の影響で、
ベトナムでは奇形で生まれる子が増えだした。
また、徴兵されベトナム戦争に従軍した兵隊の欝病(うつびょう)が増え、
自殺するものが増えていく。
戦争は、始めるときは簡単で、終わらせるのは難しい。
終わらせたとしても、後遺症で死ぬまで苦しむことになる。
多くの素朴に生きる人々の人生をずたずたにしてしまうのが、
戦争の一番の恐ろしいことだ。
■ ■ ■
「何のために自分は生まれてきたのか?」
喧嘩や戦争をするために生まれてきた赤ん坊は一人もいないのだと思う。
「何のために自分は生まれてきたのか?」という疑問を持ち続け、
その解答をしどろもどろでも追及する人々が増えることは、
きっと、ほんとうの平和な世界につながることだろう。
さらに、感謝する気持ちと他者を慈しむ謙虚な心を大切に遣いたい。
その心は人間として生きていく上で、
けっして忘れてはいけないことだと痛感する。
■ ■ ■
先日読んだ本に「ありがとう(高木善之・著)」がある。
その中に三つのありがとうが書かれていた。
アメリカの先住民族の考え方だ。
有るのが難しいのが平和な日常である。
平凡な日常にも「有り難う」と感謝しながら、
百年後の人々の幸せも考えて今日を生きるか、
自分のためだけに生きるかでは、
その人の人生は180度違うものになるように思えてならならない。
篠島 実2015-6-22夏至
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
三つのありがとう・・・高木善之
アメリカ先住民族など多くの先住民族では
「人は幸せをもたらすために生まれてきた」と考えられています。
そして人は一生の間に三つの「ありがとう」を言われるのです。
●Birthdayバースデイ(誕生)
人は幸せをもたらすために、遠い宇宙からやってくると考えられているので、
赤ちゃんは、生まれてきたとき、みんなから「ありがとう」と言われて抱きしめられます。
生まれてきたとき、「ありがとう」で迎え入れられるのです。
●Re-birthリ・バース(再誕生)
成長するにしたがって、その人の役割が発揮されてきます。その特徴をこの人の名前にするのです。
元気な子は「ブレイブ・ボーイ」、かわいい娘は「ポカホンタス」。
さらに大きくなって、一人前になると、グッドハンター(狩の名人)、メディスンマン(薬草を見つける人)など。
その名前をつける日をリ・バースデイと呼び、みんなに「ありがとう」と祝福されます。
●Give awayギブ・アウェイ(与えつくす)
これはお葬式のことです。私たちは、お葬式は悲しいと思っていますが、
先住民族は、この日は最後の感謝の日なのです。
人は幸せをもたらすためにやってきたのですから、死ぬことは、「幸せを与え尽くした」と考えられています。
だから人が死ぬと、「幸せを与え尽くしてくれて、ありがとう」と最後の感謝をするのです。
人は生まれたときと、役割を見つけたときと、死ぬときに「ありがとう」を言われるのです。
人はみんな、
幸せのために生まれてきた
幸せを与え、
幸せを味わい、人は死んでいく
毎年恒例、春の球技大会で思うこと・・・
2015年3月30日、毎年恒例の球技大会をおこなった。
研修学院の近く、川口ふれあい館の体育館を借りられ、
中学・高校生30人のみんなと汗を流し、大いに楽しめた。
ドッジボール大会とバスケットボール大会をメインに行ったが、
広い空間で、みんなやりたいことを見つけて、
仲間を集って、自由に遊んだ。
ゲーム機に普段夢中の子供たちも、
体を動かす3次元のボール遊びの方が
やはり楽しいのだろう。
みんな汗をかきながら、充実した1日となった。
■ ■
今の中学生は物質的には恵まれているんだろうが、
少々可哀想だなと思うところがある。
野球部に入れば野球だけ、
バスケットボール部だとバスケットボール漬け・・・。
僕が中学生のとき、バスケット部に入部したが、
時にはサッカー、時にはトランプ、時には登山、
ギターを練習したりといろんなことをやった。
とにかく自由だった。
何をやるかは、部員で決められた。
特にトランプゲームは頭を使う。
頭を使うことが僕らのバスケットを上達させた。
バスケットボールだけをやっていてもそれは上達しない。
体罰は決してなかった。
何が何でも優勝・・・なんて目標もなかった。
僕たちそれぞれが、自主的にバスケットを通じて、
人生を考えていく・・・自分の主体性を確立していく・・・
そのようなことが大きな目標だったと感じている。
これは顧問の先生の方針だった。
■ ■
「困ったときはお互い様・・・
仲間が失敗したら、フォローをみんなですればよい。
それができることが強いチームの条件だ。」
この言葉は未だに覚えている。
助け合うこと・・・これはニンゲンとして一番大切な精神だ。
自分さえよければよい・・・という考えに支配されている人は
決して精神の安住はない。
なぜならば、他者はみな敵になってしまうからだ。
仲間と共に幸せになる・・・この大切なことを
部活から僕は教わってきた。
そして今でもこの教えを活かして実践している。
僕はその部活を通して、きっと人間性を養ってきたのだろう。
■ ■
困ったときがあったら遠慮せずに相談に来よう。
心の闇を打ち明けて話しあえばきっと、
明日が見えてくる。どんなに暗い気持ちになっても、
さらに、闇のような夜が開けないのではないかと思い込んでいても、
朝のあけない夜はないのだから・・・。
頑張るだけが人生ではない。
時には弱い自分をさらけ出し、
悩みを打ち明けることも、
生きていく中では重要だと、つくづく思う。
(2015/4/20.篠島 実)
2015入試がんばりました!
今春の高校受験が終了した。
みんなそれぞれ入試の前日までがんばった。
今年の埼玉公立高校の入試問題も全教科難しくなったようで、
入試後の自己採点で落ち込んだ生徒も少なくなかった。
公立入試では学校の成績、内申点も半分合否に影響する。
中3の成績をアップさせられたみんなは、
そのおかげで合格できた。
日頃の行いがよかったのだろう。
日頃の行い・・・呼吸から始まり、食事や運動・・・
自分の命の健康を保つための努力は特に大事だ。
さあ、後輩たちも、日頃の行いを良くして、
がんばった先輩たちに続いて欲しい。
まずは春期講習でファイトだ。
新学年初めの中間テストで
自己ベストを大きく更新させることをイメージして、
やることをきちんとやっていこう。
がんばるみんなをいつでもどこでも
思いっきり応援するのが、
ぼくたちの役割だ!
輝く未来に向かっての2015年の春が来た。(2015/3/20篠島 実)
PS・すてきな笑顔をありがとう!♪
言葉は力を持っている
言葉は僕たちのいのちを高めてくれる。
心の奥にどんな言葉を貯めておくか・・・
それによってその人の生き方が変わるものだと信じている。
例えば、テストや仕事の結果が悪く失敗したとき・・・
「こんな結果ではもう何もかもだめだ」と思うか
「だめかもしれないけれど、
やれることから少しずつやり直していこう」と考えるか、
その後の行動は180度変わってくる。
長く生きていけば、成功した喜びの数よりも、
失敗した苦しみの数が増えていく。
失敗して自分を見失う人ではなく、
それを乗り越えようと勇気を持つ人になりたい。
嬉しい時には、思いっきり喜べばよい。
悲しい時には、
心静かに自分の悲しみと向き合うことだ、
その辛さから逃げることなく。
僕が高校生の時、詩人であり劇作家、小説家、
自然科学者、政治家、法律家だった
ドイツのゲーテ(1749年〜1832年)の言葉に
勇気をもらえたことをふと思い出した。
彼の言葉のいくつかを掲載する。
心に響いた言葉があったら、
是非、自分の手で書き写して
机の前にでもその紙切れを貼っておこう。
言葉の力を信じて・・・。(2015/2/20篠島 実)
*********************************
《生きる道》
自分自身を信じてみるだけでいい。
きっと、生きる道が見えてくる。
《焦りと後悔》
焦ることは何の役にも立たない。
後悔はなおさら役に立たない。
焦りは過ちを増し、
後悔は新しい後悔をつくる。
《軽蔑しない》
われわれは結局何を目ざすべきか。
世の中を知り、それを軽蔑しないことだ
《不幸》
本当に不幸なのは、
できることを未完のまま放り出し、
理解もしていないことをやり始めてしまう人々だ。
彼らがやがて嘆くのも無理はない。
《自由な心》
本当の自由な心とは「認める」ということである。
《節度》
節度を持った人だけが
豊かさを感じる。
《今すぐ始める》
あなたにできること、
あるいはできると夢見ていることがあれば、
今すぐ始めなさい。
向こう見ずは天才であり、
力であり、魔法です。
《すぐにはわからない》
すべてを今すぐに知ろうとは無理しないこと。
雪が解ければ見えてくる。
《本当の理想》
現実を直視する心に、
本当の理想が生まれる。
《自分ひとり》
自分ひとりで石を持ち上げる気がなかったら、
二人でも持ち上がらない
祝・成人Party at Kenshu Gakuin
成人式を迎える前日に
5年前高校受験生だった
けんしゅう卒業生が研修学院に大集合!!
祝成人式PARTYを毎年行っています。
けんしゅうで学んだことがかけがえのない
思い出になっているよ!!といわれると
ほんとうにこの仕事をしていて
よかった・・・と思います。
ところで
世界も
日本も
激動でたいへんな時代に
突入したのだと思います。
自分に、
世界に、
そしてこの日本に
するどいまなざしを向けて
生き抜く覚悟と勇気を
お互いに持っていきたいものです。
百年後の人々の幸も考えながら。
ご成人おめでとう!
HATACHI
1年は365日
20年では7305日
ものすごい時が流れた
でも人生は
まだ、始まったばかり・・・
自分というやっかいな存在を
この先も
育てていかねばならぬ
自分というやっかいな存在・・・
ほんとうに自分ってやっかいな存在だ
そんな自分を
死ぬまで育てていくのは自分しかない
みんなの倍以上生きてきた僕自身も
今でも
このやっかいな自分を
育てつづけている
明日に向かって走っていこう
時にはお酒を呑みながら
本を読むゆとりをもってね・・・ (2015/1/11篠島 実)
・・・なみだ・・・
「え」と書けばえ?って思われ、
「絵」だと、だいぶ意味が伝わる。
「絵画」と書けば、
何だか、高級なイメージになる。
このように話すのは簡単でも、
文章を書き、その言葉(漢字)を選ぶことは結構難しい。
どの言葉だったら自分の気持ちに近いか、言葉選びに悩む。
文章を上達させたかったら、
上手な人の文書をたくさん読み、
それを真似することだ。
「学ぶ」とは「まねぶ」が語源で、
真似上手な人は勉学の上達が早い。
詩人であり科学者、教育者、童話作家でもあった
「宮沢賢治」って人に猛烈に興味を持ち、手当たり次第、
彼の作品を20歳ごろからぼくは読みはじめた。
感動したことを言葉や音楽にしてみることを大切にしてきたが、
その楽しさを彼から教わったようにつくづく思う。
逢って話したことはないが、
たくさんの作品を読むことによって、
多くの時間を彼と共に過ごせたような気にさせてくれる。
これが読書の醍醐味だ。
読書の秋と冬・・・秋冬の夜長に読書を!!
読書もよいが、絵画の鑑賞も捨てがたい。
大分県に画家のさとう瑠璃さんがいる。
彼女の絵画は母と子の愛をテーマにした作品が多く、
海外からも注目されている。
作品の中に「なみだ」と題した絵がある。
この絵にはたくさんのお話しが隠されていると思え、
長い時間見とれてしまった。
言葉になれない言葉達が絵の具を通して
いろいろな光と影に表現され、
それを自分なりに解釈してみる。
この絵からひとつ詩を紡ぐことができた。
「なみだ」
喜びのナミダ
悲しみの泪
感謝の涙
慈しむなみだ。
幾つものなみだ・・・
億万、兆万、億兆万の
流した瞳のしずくの粒は
やがて海に戻り
おひさまに照らされ
雲となり
山にぶつかり
雨となる。
何十年後か
再びわたくしたちの身体に戻ったとき
わたくしたちは
前回より
さらに輝くナミダを
泪を
涙を
なみだを流せる
人となれる。
絵を描く、曲を創る、言葉を紡ぐ・・・
ニンゲンの重要な能力である。
与えられる音楽や言葉を消費することだけで人生を終わらせるのは、
人として生まれてきたのにもったいない。
塾生のみなさんの多くが創作に目覚めて欲しい2014年の晩秋である。(2014/11/20)
たのしかったボーリング大会
毎年恒例、夏休みのボーリング大会。
テーマは、集中することの大切さ・・・
集中しないとボールはまっすぐに転がらない。
しかし、集中しようと緊張しすぎれば、
あるいは、何が何でもスペアーをとるぞと、
肩に力が入り過ぎれば、溝に落ちてしまう。
なかなか思ったとおりに転がらない。
成績アップを目的にした学習でも、
同じことがいえるかもしれない。
テストでハイスコアーを出したかったら、
まずは、重要事項の暗記だ。そして問題をひたすら練習。
自分の脳みそと手を使ってみないことには仕方がない。
人のやっているのをいくら見ていても決して上達しないボーリングと同じように。
夏期講習後半戦・・・自分の実力をアップさせるためにラストスパートだ。
Fight!! (2014/8/21篠島 実)
珊瑚礁の化石の山、武甲山

2014.6.1、埼玉県秩父の武甲山に友人と登ってきた。
上の写真は標高1304mから秩父盆地を魚眼レンズで撮影したものだ。
「地球は緑の命に覆われた惑星なんだ」・・・といたく感動した。
下界は30度を超す猛暑だったが、山頂は涼しい風が吹いていた。
100m登ると0.6度気温が下がる。では、1000mだと・・・
100m:0.6度=1000m:χ度・・・
こういう時に比の考え方はありがたい。
これを解けばχ=6 ・・・・・・6度も低くなる。
6月にしてはとても空気が澄んでいて、
遠くは谷川岳や日光の山々、福島の山々も見ることができた。
こういう風景に出会えたとき、
心の中のもやもやもどこかへ吹き飛んでしまい、
何ともいえない清々しさが全身を包み込む。
だから山登りはやめられない。
重力に逆らって登るのはしんどいのだが、
山頂にたどり着いた時の達成感は言葉では言い尽くせない。
エレベータで634mまで登るスカイツリーでは
決して味わうことのできない感動なのだと思う。
生きていることの尊さとその喜びを新緑の木々や、
小鳥たちと共有できることも山登りのすてきなところだ。
山の中はすべての命がいきいきと息づいている。
▲ ▲ ▲
この武甲山はかつてハワイの方にある海底火山だった。
火山活動が終わり、その後、珊瑚礁が繁茂。
それが太平洋プレートの移動とともに埼玉県まで来て、
2億年前に起き上がるように隆起した。
珊瑚礁はその地殻変動の際に化石となり石灰岩となった。
富士山の誕生が10万年前。
2億年前と10万年前では時の流れは雲泥の差であり、
武甲山で進化した動植物が少なくない。
特に、絶滅危惧種のチチブイワザクラや
ミヤマスカシユリが有名である。
武甲山はいわば日本のガラパゴスといえる。
また、武甲山に巨大な貯水タンクの役割があることを考えれば、
山の内部には大鍾乳洞があり、大地底湖もありそうだ。
どんなに日照りが続いても、
武甲山の伏流水は途絶えた試しがないことや、
目のない魚が山の近くで釣り上げられたことから推測できる。
▲ ▲ ▲
日本の石灰岩の山は北九州の英彦山(ひこさん)から
四国・鳥形山、滋賀・伊吹山、埼玉・武甲山、
群馬・叶山(かのうさん)をたどって東北まで点在している。
どの石灰岩の山も2億年前に誕生した。
その石灰岩の山を結んだ線の近くが、
日本列島の中央構造線断層があり恐怖の活断層である。
ところで、セメントの原料は石灰岩。
石灰岩の山のほとんどが削られ、砕かれ、
貴重な生態系が破壊されつつある。
生物多様性の中で人間は進化し、
文明を築いてこられたことを考えれば、
自然破壊は程々にする決断がそろそろ必要となる。
自然破壊のなかでも最たるものは放射能汚染。
未だ収束しないフクシマ原発の方向に向かって、
祈りを捧げることしかできない自分を悲しく思った。
2011.3.11以降、
故郷を追われて避難している13万人以上の方々のことを
決して忘れてはいけない。 ( 2014/6/21夏至 篠島 実 )
PS・中高生は、期末テスト直前!
自己ベスト更新をめざして必死にテスト勉強に取り組もう。
受験も山登りと同じだ。
一歩踏み込んで登り詰めていこう!
受験がんばりました!(2014/3/5)

祝・成人Party at Kenshu Gakuin
毎年恒例、研修学院での成人を祝うPartyを
1月12日に行った。
みんな大きくなったな、、、がんばったね。

2014/1/12研修学院にて
日本最古の物語で、
不死の薬が燃やされた、ということは・・・
中1の国語で必ず学習する「竹取物語」、
日本で最も古いものの語り(物語)だ。
一番のクライマックスは、最後のふじの煙の段。
月に還るかぐや姫が帝に不死の薬をプレゼントする。
申し訳ない気持ちを最大に表した。
しかし、帝は「会ふこともなみだに浮かぶわが身には死なぬ薬もなににかはせむ」と歌に詠み、
駿河の一番高い、月に最も近い山に兵士をたくさん登らせて、この薬を燃やさせてしまう。
不死の対義語は必死・・・自然災害の多いニッポンでは、
地震や津波、火山の噴火、台風、土砂崩れでいつ死ぬかわからない。
今を大切に、一日を一生と思い、必死になって生きよ、
という教えが含まれているのだと解釈している。
中間テストが終わった後に、テスト勉強しても仕方がないのだ。
何事にも最終の締切がある。
このことを意識すればもっと必死になって打ち込めるのではないだろうか。(2013/11/20)
竹取物語【ふじの煙】
そののち、翁・嫗(おうな)、血の涙を流して惑へどかひなし。
あの書きおきし文を読み聞かせけれど、「なにせむにか命も惜しからむ。
たがためにか。何事も用もなし」とて、薬も食はず、やがて起きも上がらで、
病み伏せり。中将、人々引き具して帰りまゐりて、かぐや姫を、え戦ひとめずなりぬること、
こまごまと奏す。薬の壺に御文添へ、まゐらす。
広げて御覧じて、いといたくあはれがらせたまひて、物も聞こし召さず、
御遊びなどもなかりけり。大臣上達(かんたちべ)を召して、
「いづれの山か天に近き」と問はせたまふに、ある人奏す、
「駿河(するが)の国にあるなる山なむ、この都も近く、天も近くはべる」と奏す。
これを聞かせたまひて、
会ふこともなみだに浮かぶわが身には死なぬ薬もなににかはせむ
かの奉る不死の薬に、また、壺具して、御使ひに賜はす。
勅使には、つきの岩笠(いはかさ)といふ人を召して、
駿河の国にあなる山の頂に持てつくべき由仰せたまふ。
嶺(みね)にてすべきやう教へさせたまふ。
御文、不死の薬の壺並べて、火をつけて燃やすべき由仰せたまふ。
その由承りて、士(つわもの)ども富(あまた)具して山へ登りけるよりなむ、
その山をふじの山とは名づけける。
その煙(けぶり)いまだ雲の中へ立ち上るとぞ言ひ伝へたる。
(現代語訳)
その後、翁も嫗も、血の涙を流して悲嘆にくれたものの、何の甲斐もなかった。
あのかぐや姫が書き残した手紙を読んで聞かせても、
「どうして命が惜しかろうか。
いったい誰のためにというのか。何事も無用だ」と言って、
薬も飲まず、そのまま起き上がりもせず、病に伏せっている。
頭中将は、家来たちを引き連れて帰り、
かぐや姫を戦いとどめることができなかったことを、
事細かに奏上した。薬の壺にかぐや姫からのお手紙を添えて差し上げた。
帝は手紙を御覧になって、たいそう深くお悲しみになり、
食事もお取りにならず、詩歌管弦のお遊びなどもなかった。
大臣や上達部(高級官僚)をお呼びになり、
「どこの山が天に近いか」とお尋ねになると、お仕えの者が奏上し、
「駿河の国にあるという山が、この都にも近く、天にも近うございます」と申し上げた。
これをお聞きになり、
《もう会うこともないので、こぼれ落ちる涙に浮かんでいるようなわが身にとって、
不死の薬が何の役に立とう。》
かぐや姫が献上した不死の薬に、また壺を添えて、
御使いの者にお渡しになった。勅使に対し、
つきの岩笠という人を召して、
駿河の国にあるという山の頂上に持っていくようお命じになった。
そして、山の頂でなすべきことをお教えあそばした。
すなわち、お手紙と不死の薬の壺を並べ、
火をつけて燃やすようにとお命じになった。
その旨をお聞きし、兵士らを大勢連れて山に登ったことから、
実はその山を「富士の山(士《つわもの》に富む山・不死の薬を燃やした山)」と名づけたという。
そのお手紙と壺を焼いた煙が今も雲の中へ立ち上っていると言い伝えている。
食育の大切さ
食生活を見直したきっかけ
いよいよ癌かも知れないと思うぐらい今年2月に胃腸を壊してしまった。
高校受験直前なので、医者に行く時間がないし、
検査のためにX線でたくさん被曝するのも嫌だと思い、
まずは日頃の食生活を見直すことにした。
1日に玄米一合と味噌と少しの野菜
外食とコンビニ弁当に頼ることをやめ、
10年前に教室で買って最近ではほとんど使わなくなってしまった炊飯器で
玄米ごはんを炊き、味噌と少しの野菜をいただく日々を送った。
玄米は完全に無農薬のものを手に入れた。
そうでないと玄米食はかえって身体に悪いと聞く。
白米は精米時に農薬も剥ぎ取られるが玄米は精米をしない。
普通に炊けば、硬くて、胃腸をかえって悪くするとも言われるが、
一晩水につけて炊けばやわらかくいただける。
化学的物質を極力体内に取り込まない
大好きだった牛乳・肉をやめ、タンパク質は大豆からとるようにした。
味噌や醤油も昔ながらの自然農法で2年以上発酵させて作ったものに思い切って切り替えた。
味噌も醤油も作るときには塩が必要なので、
化学的塩(食卓塩)ではなく海水100%の天日塩を使用しているものにこだわった。
お酒は焼酎、ビールをほぼ呑むのをやめて、
化学的アルコール(醸造アルコール)の入っていない2年以上発酵させた純米酒をしたためた。
とにかく、化学物質を極力体内に取り込まないように努めることに心がけた。
胃腸が悪くなったらほとんどの医者はお酒を辞めるように指導するが、
化学的に作る醸造アルコールが悪いのであって、
昔ながらの日本酒は百薬の長であることを信じている。
食欲がなく、エネルギー不足になりがちだが、程よいカロリーを身体に与えてくれる最高の流動食だ。
さらに腹六分目を心がけ、それを半年以上続けたら、
なんと体重が15kgダウンし、ウエストは12cm引き締まり、
体重が減った分、身体が軽くなり、そして、すっかり胃腸の健康が戻った。
今では胃腸薬を飲まずに過ごせるようになった。
危険な食べ物があふれている現代
薬に頼らず、食事療法で慢性の病気は治せることを、身を持って体験した。
化学が発達し、塩も砂糖も、手間をかけずに化学合成で大量生産される現代。
味噌や醤油、酒は熟成させずに化学的に安価に作る。
科学が発達していなかった江戸時代はどこで食事をしても安全だったが、
現在は危険な食べ物があふれているように思えてならない。
若い人は浄化作用が強いので、悪いものは早く排出されるが、
歳をとった者は新陳代謝が鈍くなり身体に害の化学物質はいつまでも留まり、蓄積されていく。
集中力に影響を与える日々の食事
毎日の食事は、集中力に大きな影響を与えると言われる。
よく噛んで食べる子は集中力が増し、少ない量で満腹になる。
腹八分目なので、食事の後に眠くならず、集中して勉強ができる。
34年間、学習塾で仕事をしていて、成績の良い子どもの共通した傾向は、
毎日の食事の充実にあるのではないかと感じている。
そして、海水100%の塩にこだわって料理を作られていることも強い相関関係がありそうだ。
食育によっても成績アップ
塩分の取り過ぎは良くない…と言われて久しいが、
正しい塩をある程度多めに摂らないと身体の抵抗力は弱まる。
さらに、たくさん汗をかく子どもは常に塩不足の状態になって、
集中力にも影響を与える。成績アップに向けて、食育はとても重要だと最近強く思うようになった。
2013/9/19 十五夜の月を見ながら 篠島 実
PS・2学期の中間テスト成績アップに向けてFight!
食欲の秋だけれども、豚みたいにガツガツ食べず、
よく噛んで食べ、腹八分目を意識して集中力を増強させよう。
今こそ心の支援を
お盆休み、川口より500km離れた気仙沼・大島復興の支援に行ってきた。
NPOアトリエパンセの方と共に
「子どもたちの未来に希望を…」をテーマに掲げ今回で5回目となる。
昨年以来顔なじみになった地元の人達に
「遠いところから暑い中よく来て下さった」と、喜んでいただけ、長旅の疲れも吹っ飛ぶ。
昨年の3.11から17ヶ月経ち、被災地はこれからが正念場を迎える。大した支援はできないが、
現地を訪れ、被災者のその後の話を聞くことが大切だ。
心の支援が今とても必要なのだと感じた。
津波による重油流出で火災のひどかった気仙沼ではがれきがすっかり片付き、
夏草がそこここに繁茂していた。
しかし、漁港から約500m陸に打ち上げられ、
焼けただれた巻き網漁船「第18共徳丸」(全長約60メートル、330トン)が
その津波と火災のものすごさを今なお物語っている。
3.11津波被害の象徴として、
原爆ドームのようにモニュメントとして残す計画と、
取り壊す考えと半々のようだ。
津波で被害を受けた人たちの中には、
その巨大漁船を見ると津波を思い出してしまい解体を望む声も多いと聞く。
原爆ドームもそのような意見がずいぶんあった。
しかし、67年後の現在、そのドームを残した意義は大きい。
二度と原爆の使用を許さないためにも原爆ドームは今後も活躍することだろう。
現在生きているぼくたちの大きな一つの使命は、
未来に有意義な何かをバトンタッチしていくことだ。
気仙沼の巨大漁船は3.11の津波のものすごさを
未来人に伝えるモニュメントになることだろう。
どうしようもない悲しみを少しでも癒せるような
慰霊の意味を込めた大きな公園にするのも一案だ。
そのようなことを地元の市会議員さんと話し合ってきた。
気仙沼から離島の大島にはフェリーで20分。
昨年の夏よりもカモメの数が増えていた。カモメも復興を心から応援している。
大島のがれきもずいぶんと片付いていた。
快水浴百選の美しい小田ノ浜に海の家が仮設でオープン。
緑の真珠…気仙沼大島も少しずつ復興してきた。(2012/8/21 篠島 実)
ハロードリーム
先月、友人から『ハロードリーム』なる存在を教えてもらい、
さっそくホームページを検索。
そして、次のようなメッセージに感じるものがたくさんあった。
*****(引用はじめ)***********************
こどもの限りない可能性は何ものにも代えがたい宝物です。
こどもは誰もが夢【vision】を描く力を持っています。
そして、その夢に一心に立ち向かう力を兼ね備えています。
未来を担うこどもたちがいきいきと夢を描き、
喜びをもって学習や遊びを楽しめる環境を創ることが大人の使命です。
すべての人が「生まれてよかった」と思える世界を実現するために
その第一歩として『こどもの夢をはぐくむ社会になる』ことを目指し
ハロードリームプロジェクトを立ちあげました。
ハロードリームは『夢』を通して
《こども・大人・企業・地域・世界》をつなげる
『かけはし』となります。
こどもたちの明日が
平和で希望にあふれたものとなりますように。
******************(引用おわり)
こどもはこの宇宙が授けた「宝物」・・・まさにそのとおりだ。
現在、多少勉強ができなくても、運動ができなくても、
さまざまな可能性を持った存在だと僕も思う。
自主的にやりだせばどの子も上達するのは早い。
春のお日様のようにあたたかく見守ることがまず大切である。
こどもたちが生き生きしている社会は
大人にとっても、老人にとっても幸せな社会なのだから。
100年後に生まれてくるこどもたちを悲しませないことを目的に、
環境問題や食糧問題、エネルギー問題を僕らは考え、
取り組まなければなければならない。
自分達さえよければいい・・・という考えから、
遠くの人類の未来にもまなざしを向けるこころのゆとりが、
今、僕たちに求められているのだろう。
さっそく、研修学院も少しばかりか寄付し
『ハロードリーム・サポーター』にさせていただいた。
送られてきたハロードリーム憲章は、研修学院の塾生心得に追加したいと思う。
世界中の人たちの希望にもつながる言葉がたくさん詰まっている。(2010/4/20 篠島 実)
ハロードリームについては次のホームページで確認できます。
http://hello-dream.com/
いま埼玉を生きる
「いま埼玉を生きる」という本(埼玉日報社)が出版された。
埼玉日報新聞が昨年企画したコラムをまとめた本で、埼玉県に根ざして活躍している35人を紹介している。
その35人のなかに僕も入らせていただきとても嬉しい。その出版記念パーティーが先日催され出席してきた。
新都心にあるお洒落なイタリアンレストランでのパーティー。イタリアン料理のフルコースは初めてだった。
夏向けの味付けでどの料理もさっぱりしてとても美味しかった。
美味しい料理をいただくと、会話もはずみ、心が豊かになった気分になる。
このパーティーに集まった人たちの活動はするどく、地域に根ざして生きてきた人たちの顔はいきいきしている。
グローバルな分野で出世することが多くの現代人の夢だったりするが、
ローカルにスローに生きていくことも豊かな人生を創り上げていくことになると再確認できた。
グローバル化はいろいろな弊害を増産している。食糧問題を考えてみてもグローバル化による弊害は大きい。
自分達が食べるものは自分達の地域で作り消費することを基本にして生きていくこと…これは一つの哲学となるだろう。
食料の自由化に伴って、豊かな国には食料が余り、貧しい国では今でも飢餓に苦しんでいる。
この国ニッポンでは1年間で国民が食べる量と同じ分だけ廃棄していると聞く。
売れ残り、賞味期限が切れたら捨てなければならない。
作る人の顔、食べる人の顔が見えなくなっている分、食べ物を大切にする感覚が麻痺しているのだろうか。
グローバル化の大きな問題として臓器売買がある。
今夏、話題になっている映画、阪本順治監督「闇の子供たち」(宮崎あおい出演:主題歌は桑田佳祐「現代東京寄譚」)で衝撃を受けた人も少なくない。
タイなどの貧しい国では、今でも子どもが売買され、売られた子どもは先進国のお金持ち達に利用されているのだ。
臓器移植の医学が発達し、1分1秒でも長生きをしたいお金持ちの人たちのために、
タイの子供たちの臓器が狙われている現実をこの映画は世界にアピールしている。
この映画から、ますますグローバル化に対して疑問を増幅させたやさきの、出版記念パーティーだったのだ。
学校に行けなくなってしまった子供たちを育てるフリースクールを運営している方、食の安全をアピールしている人、
全国の中学校から業者テストを排除した、元埼玉県教育長…などなど…いろいろな分野の人が集まった。
そのなかでも、僕と同い年のイスラエルの人と仲良くなった。
日本の木造建築に見せられ、秩父に木工房を営み、伊勢神宮の神棚を最近つくったほどの腕のある人だ。
古き日本の木造の伝統を日本人以上に守っている。
グローバル化によって人と人との交流が盛んになりこのようなよい結果も生まれる。
しかし彼は秩父というきわめてローカルの土地に根ざして、なんと、伊勢神宮の神棚を依頼され、そして、りっぱに作りあげた。
これから自分の人生を創り上げていく塾生のみなさんにもちょっと立ち止まって考えて欲しい問題が「グローバルとローカル」である。
生き方を180度変える問題だからだ。
出版記念パーティーに来られた50人の前で僕は「武甲山」をギター片手に弾き語ってきた。
いま埼玉を生きる人たちから大きな拍手をもらえた。
今年の夏の大きな思い出である。 (2008/9/1 塾長)
心を込めて
ボール
ボールは心を持っている
選手のイラつき、思いやり
ボールはその感情を感じとり、放たれる
曲がった心で放ったボールは
曲がって飛んでいく
真っすぐな心で放ったボールは
真っすぐ飛ぶ
心の込もったパスは捕りやすい
心の込もっていないパスは捕りにくい
その「心」がプレイを大きく左右する
僕は「心を込めて」という言葉が好きだ
スポーツをする上で一番大切なことだから
そして今日も、大好きなバスケットをする
「心を込めて」
中3の塾生で末武君創作の詩が文集川口に載った。それも、巻頭に・・・とても名誉なことだ。
心から祝福したい。
上の詩を読んで心がとても温かくなる思いをした。僕らは普段の生活でどれだけ心を込めて生きているのだろうか・・・
自らを省みるととても恥ずかしい気持ちになる。
心を込める・・・その一番説明しやすいことが「パス」であったことに新鮮さを感じた。
言葉も一つのボール投げと同じで、相手に正確に伝わるように使わなければならない。
そのときに大切なのは「心を込める」ということなのだろう。
「心」・・・とても複雑な4次元空間的なつかみ所のない実体である。「心は自分の身体のどこにあるのか?」
僕の心は心臓の近くにあったり、みぞおちの辺りにあったり、
ギターを弾いているときは両手の指先に移動したり、
すてきな風景を眺めているときは目の中に・・・と僕の体中を動き回っているように思える。
または、授業中は身体から飛び出して生徒一人一人のそばにいってみたりすることもありそうだ。
感じ取り方を「感性」という。末武君のバスケットに対しての感性はすばらしいし、鋭い。
そして、人を感動させる感性ももっている。
なによりも心を込めて書かれているので、感動的な詩だ。
塾生のみなさんも、日常の他愛もないことを自分なりの感性で「心を込めて」言葉をつづってみよう。
考えることは、言葉を並べることだ。文章を書くことは考えることだ。
話し言葉中心の携帯メールばかりでなく、しっかりした書き言葉をつづってみよう。
それは、人として生きていく上でとても大切にしていかなければならないことだから・・・ (2007/9/20 篠島 実)

たくさんある、原人に学ぶこと
縄文時代よりも前の時代は旧石器時代と呼ぶ。
今から2万年前の時代である。
突然だが、旧石器時代の人たちと現代の僕たちを比較してみよう!
例えば、「おなかがすいたら」・・・
現代人は、お財布を持ってコンビニへ行けば何か食べ物を買えるが、
旧石器時代にはコンビニがない。
貨幣経済のシステムもないので、食べ物は自分で探さなければならない。
ねずみやもぐらのような小さいやつよりマンモスみたいな
ナウマンゾウをしとめられれば当分おいしいご馳走にありつける。
でかいナウマンゾウをしとめるには自分一人ではとても無理。
仲間を集めて話し合い作戦を練る。
ナウマンゾウをしとめるためにそいつらの行動パターンを観察し、しっかりと記憶する。
もの覚えの悪いやつはこの時代を生き抜くことができない。
だから・・・みんな記憶力は相当あったと思われる。
みんな生きていくのに必死だから、当然といえば当然だ。
車や機械類は一切ないので、自分の腕力や脚力が頼りだ。
まさに実力主義の時代だった。

ところで、子どもの教育はどうだっただろうか・・・
学校はない。
義務教育もない。
親が狩りの仕方を子どもに実践のなかでしっかり教えていかなければ、
親が死んだら子どもは一人で生きていくことができない。
平均寿命は35歳以下なので、親も必死になって子どもを育てたことだろう。
一人前になるように願いを込めたことだろう。
言葉はそれほど発達していなかっただろうから、
言葉で教えるよりも親がお手本を見せて学ばせるしかなかった。
そして、子どもが自然に育っていくことを見守るしかなかった。
そこには確実に父母の大いなる子どもへの愛が存在していたことが想像できる。
旧石器時代から2万年たった現在、
人間は月まで行ける科学技術を手に入れた。
しかし、子どもに対しての愛はどうだろうか・・・。
言葉だけの貧弱なものになっていないだろうか・・・。
知らずに言葉の暴力を投げつけてはないだろうか。
「願うこと。手本をみせること。学ばせること。見守ること。」
旧石器時代の人たちを想像して得られた4つのキーワード・・・
子どもと接する僕たちもこのキーワードを大切にしていきたいと思う。
ところで、谷川俊太郎(1931年東京生まれ)の作詩の中に
「あい」というのがある。僕のお気に入りの一つだ。
あい 口で言うのはかんたんだ
愛 文字で書くのもむずかしくない
あい 気持ちはだれでも知っている
愛 悲しいくらい好きになること
あい いつでもそばにいたいこと
愛 いつまでも生きていてほしいと願うこと
あい それは愛ということばじゃない
愛 それは気持ちだけでもない
あい はるかな過去を忘れないこと
愛 見えない未来を信じること
あい くりかえしくりかえし考えること
愛 命をかけて生きること
PS/旧石器人のごとく、大自然に謙虚であって、
そして意欲的に勇気を持って自分自身を生きていく人になろう!!
そして、学年末テストでレベルアップを!!(2007-2-21篠島 実)